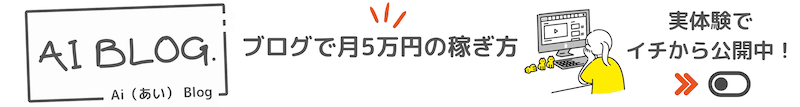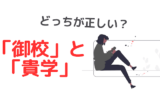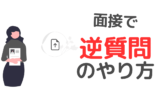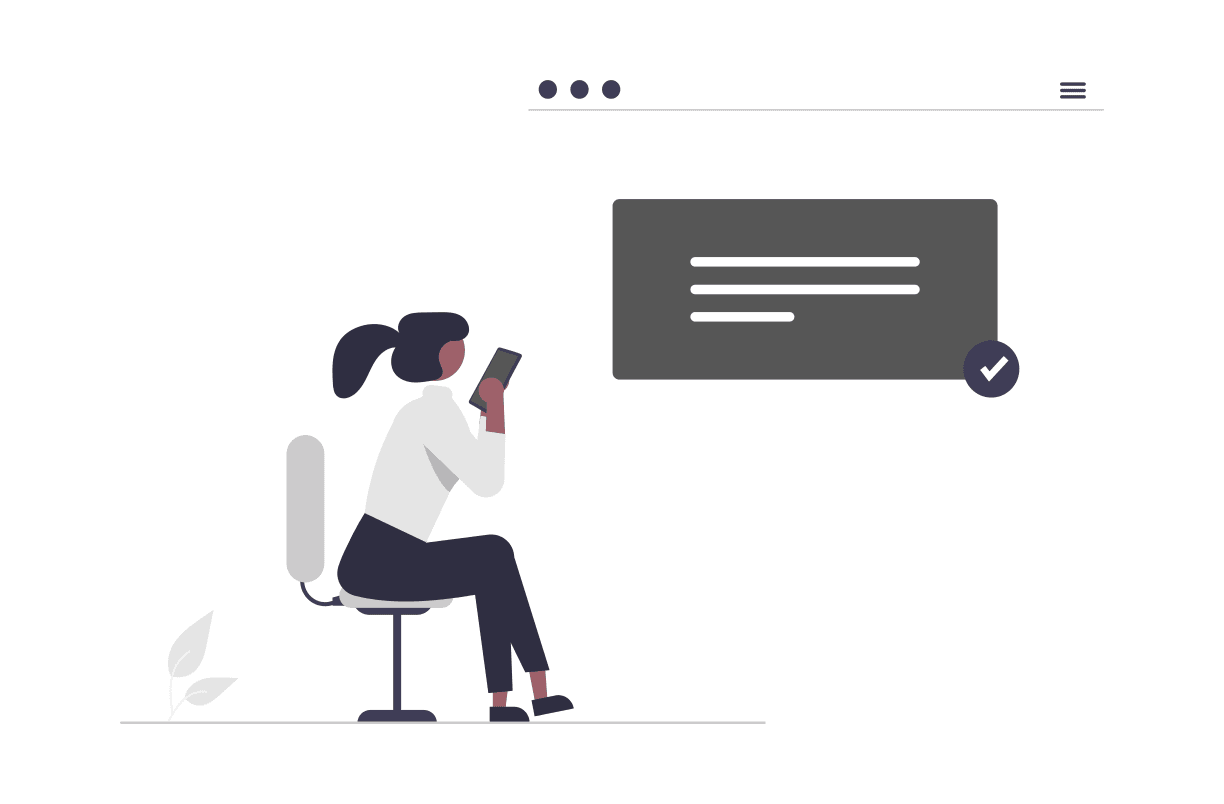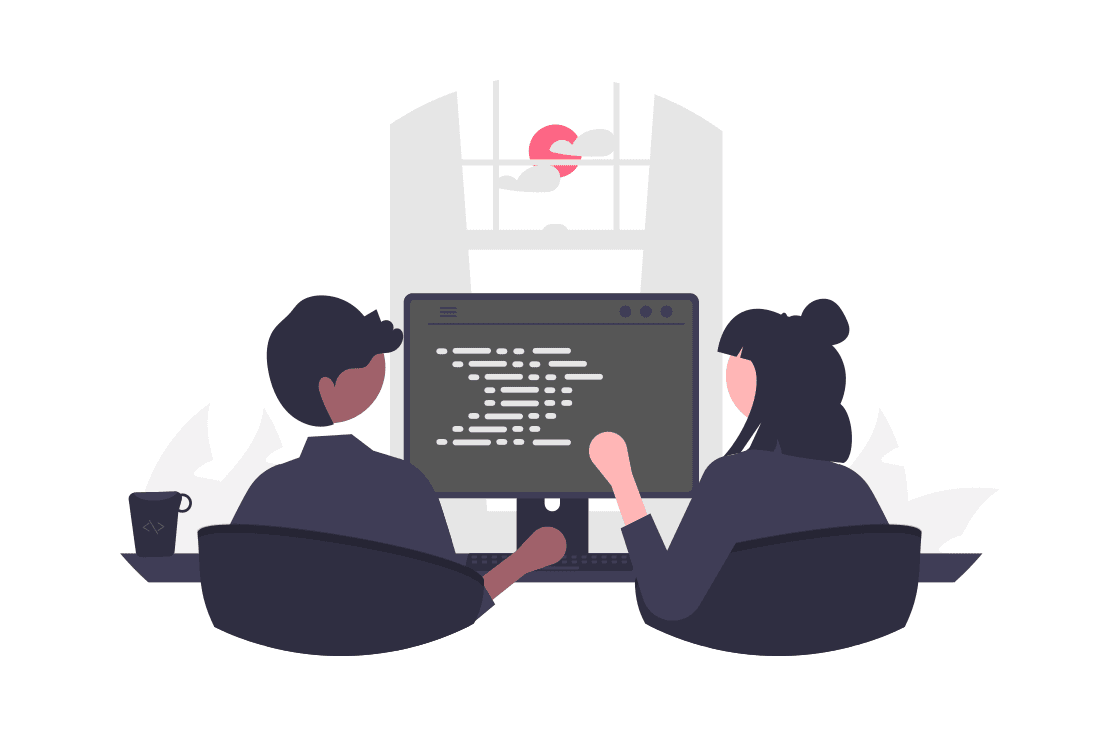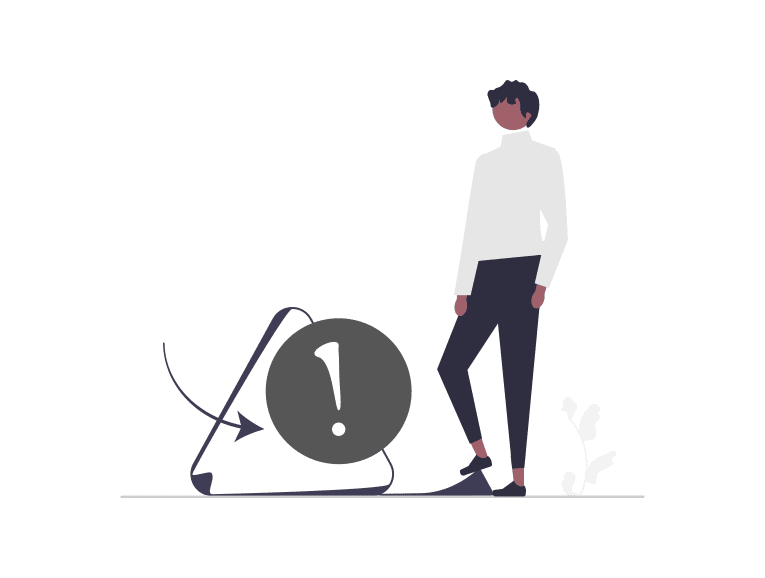
ようやく見つけた大学職員の採用に落ちてしまいました。
何が原因だったのか、理由を具体的に知りたいです。

この記事はそんな悩みにお答えできます。
大学職員の面接に落ちる理由を失敗例でケーススタディしよう
面接をする側として、全く採用する気になれないパターンを10個紹介します。
思い当たる点が4つ以上あれば、この先いくつ応募しても厳しいでしょう。
元大学職員のAI(あい)です!教務、国際、研究支援、経理、人事、学長室、と経験して20数年。早期退職を利用して引退。大学職員としての経験談をPR記事として公開中!
早速本題に入ります!
落ちる理由【1】学長名を知らない応募者
まずは、大学長の名前さえおさえないまま面接に臨む応募者が、7割程度存在します。
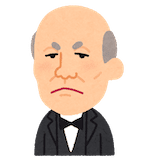
(面接官)「本気で私立の教育機関で働きたいと思ってんのかな・・」
というのがその時の面接官心理。
この手の応募者があまりに多いので、
(面接官)「あぁ、またこのタイプか・・」
と無意識のうちに不合格集団と一緒にしてしまいます。
※1次面接だと、面接官は1日に10人以上面接、それを3日ほど続けています。
事前対策をしてくる応募者
逆に、そのレベルの基本事項は当たり前のようにインプットして面接にくる応募者たちが残りの3割。
そういった応募者たちは、その時点で合格ゾーンに入ってきます。
理由は、
基本事項を事前に準備・理解して本番に臨む姿勢は、まさに事務職員の潜在適性と映るからです。
ここがわかっている応募者は、学長名だけではなく、学長の所属学部や簡単な専門領域までサラッとアウトプットしてアピールしてきます。
基本情報をおさえる
学長の名前はあくまで一例です。
例えばその他に、
- 学部の数、大学院の名称
- 主要キャンパスの名称と場所
- 付属小中高等学校の場所と名前
- 総学生数、学費
- 建学の精神、創立者のフルネーム
何らかの新しい物事に取り組むときに、基本知識を当然のように事前準備しておくのが職員力のアピールです。
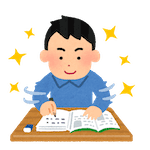
※いわゆる「まじめキャラ」のイメージですね。
面接は簡単に差別化される
面接では、この程度をおさえておくだけで他の応募者と明確に差別化できます。
準備は大変ですが、内定者は的確に対策をとってきています。
繰り返しですが、
本番前に、基本事項をマメに事前準備するのが職員力です。
準備が甘い人は、どんなに輝かしい経歴を持っていたとしても、大学職員の面接では秒殺です。
「準備が甘い」
そのこと自体、事務職員としての潜在適性が欠けているからです。
続いて「落ちる理由」の二つ目です。
落ちる理由【2】「大学」と「学校法人」の違いがわかっていない応募者
「大学」と「学校法人」の違い。
この質問は難易度が高いです。
大半の人は「質問の意味さえわからない」ような反応をします。
内定に至る人の特徴
こんな時でも、内定に至る人の特徴は次のとおり。
いかに内定者でも、明確な答えはできません。
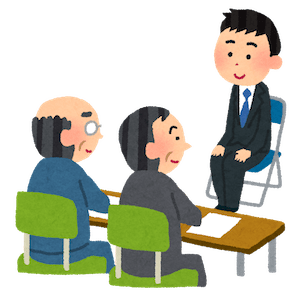
ですが、そこから派生する会話を通して、面接官は色々と読み取れます。
例えば、組織図や事業報告書などを事前に読み込んできている応募者は、そこで得た知識を苦しいながらも色々と話してくれます。
結果、
- 学校法人としての正式名称は「学校法人●●学院」
- 大学としての名称は「●●大学」
例えばそれくらいは苦し紛れにでも答えます。
- 「理事長」
- 「学長」
この違いくらいもコメントできるはずです。
そんなやりとりを通して、「大学」と「学校法人」の違いは答えられなくても、
事前に大学のことを研究してきていることが会話を通して伝わってくるのです。
これで十分なんです。
間接的な志望動機になる
それで十分な理由は、
本番前に、基本事項を事前準備してくる姿勢が職員の適性だからです。
先ほどと全く同じ理由ですね。
さらに、
よく調べていること=本気で応募していること、という印象にも繋がります。
事前準備は、間接的な志望動機としても機能しますよ。
※大学と学校法人の違いについては「大学職員の探し方【転職時に確認すべき10のポイント】」で言及しています。
面接官の質問意図
難易度が高い質問をする面接官の意図は、上記のように、
あなたの事前準備の程度を見極めるためです。
準備が甘い人はただただ硬直するだけ。
関連情報や周辺知識さえ、答えることができません。
つまり、その時点で大きなマイナス、そこから挽回するのは至難の業です。
落ちる理由【3】「学生のために」というフレーズを使う応募者
続いて3つ目の「落ちる理由」です。
学生に直結する業務は少数
職員の主な役割は、規約などの制度に基づいて学内組織を不備なく運営させることです。
規定や定款と呼ばれるルールを隅から隅まで把握。
そして、それに沿って組織内が動くように関連部署と調整を進める役割、とも言えます。
つまり、職員が、直接学生のために何かをするというシチュエーションはほとんどありません。
NGワードに注意
にもかかわらず、
(応募者)「学生のためになるような改善を色々と推し進めたい」
とかコメントされると、とても残念な印象につながります。
もはや NGワードと言ってもよく、実際、
不合格者が多用するフレーズです。
下調べや根拠が乏しいまま本番にのぞんでくる時点で、
(面接官)「仕事も、イメージや感覚だけで進めるタイプかな」

といった感じのマイナスイメージにつながりやすいです。
その他のNG発言
その他、
- 「就職サポートで学生の役にたちたい」
- 「留学経験を生かして大学の国際交流に貢献したい」
なども、残念な印象につがるNGコメント。
理由は同じです。
職員の仕事はもっと別のところに焦点があることを認識しないまま、表面上の知識で本番に臨んでいると思われるからです。
「別のところに焦点がある」と言われてもピンとこない人は、こちらの記事で霧が晴れますよ!
落ちる理由【4】カウンター越しに見えるスタッフのことを職員だと思っている応募者
学生時代の印象だけで、大学組織について軽率に発言しないようにしましょう。
学生部や就職部の印象に注意

学生部や就職部で目にしたことがある印象だけで、それを職員だと思って話す応募者はNG寄りです。
学生の目につく業務はごくわずか
実際はカウンター越しの職員は全体のほんの少数です。
そもそもカウンター業務等は派遣職員が請け負っているケースも多いです。
本質の理解力が疑われる
この手のコメント、つまり、学生時代の印象だけで大学をとらえてしまう応募者は、本番への対策がなく、手持ちの知識だけで面接に臨んでいる印象につながるので、要注意です。
落ちる理由【5】職員の仕事をデスクワーク中心だと思っている応募者
職員の業務は、結構な割合で肉体作業があります。
学内はイベントが多い
教授会の準備や入試イベント対応などで、会議室や屋外での要員対応も。
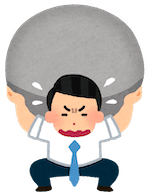
例えば、入試期間中は、何万件という問題や答案を台車に載せて、長距離を運んで、、といったこともやります。
※入試という機密性が高い業務は、正職員にしか任せられません。
さらに、AO入試や留学生入試などは9月入学。
入試は真夏に行われるので、猛暑下での肉体労働は本当に大変です。
入試課の仕事内容を把握しておくと面接では役立ちます。
ブルーカラーな業務が多い

管財課の仕事なども、作業服を着ている時間帯の方が多かったりします。
総務部も教務課も卒業生関連部署も同様で、結構ガテン系業務は多いです。
主に屋外で、運ぶ、受け付ける、誘導する、設営する、撤去する、といった感じの労働が多いです。
「大変な仕事」とは?
(面接官)「大変な仕事もあるけど大丈夫ですか?」
といった面接官のコメントは、上記のような背景を示唆しています。
そこにピンとくる応答ができるようにしておきましょう。
落ちる理由【6】「新しい提案をしたい」というフレーズを使う応募者
大学をより良いものにしたい、という趣旨で、このコメントも多いです。
新しい提案?
しかし、職員はそういったことに関係ありません。
例えば、
「新しく付属小学校を都市部に開設し、小学校レベルから富裕層や著名人の子供を取り込み、大学卒業後の寄附金戦略や大学のブランディングにつなげたい」
とかいった「新しい提案」。
大学職員に提案力は不要
こういった判断には、職員は関係ありません。
理由は、大学経営は教員が行うことだからです。
あくまでそれが決定事項となった後に、行政手続きや資金繰りなど、事務的な動きで奔走するのが職員の役割です。
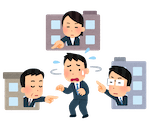
そもそも、学外者による新規提案や改革案は、学内関係者にとってはどれもチープなものに聞こえがちです。
面接時に、改革のアイデアをコメントすることはあまりにもリスクが高いことを認識しておきましょう。
あえて新しい提案を聞かれることはある
とはいえ、面接官によってはあえてそのような質問をしてくるケースもあります。
(面接官)「あなたが職員になったら、この大学をどのように変えていきたいですか?」
といった感じの質問ですね。
聞かれた場合の対策として、以下の記事でおすすめの書籍を紹介しています。
この記事は、個人的にかなり役立つ記事だと思います。知っておくと確実にコメントのクオリティが上がりますよ!
落ちる理由【7】ネガティブ応募
今の仕事がブラックで大変だから、と伝わってしまってはNGです。
働かない職員が多い温室の世界

楽をしたいから職員を受けているという本心が伝われば、その時点で面接官側は冷めてしまいます。
働かない職員がたくさんいるのが大学職員の温室世界。
(面接官)「いずれ、ああなるタイプかな」
といったような心象ができるからです。
現職をポジティブに表現しよう!
とにかく面接では、
今の仕事をどれだけ頑張っているか
ここを、まず猛アピールしてください。
教育機関で働きたい!をアピールしよう!
その延長線上で、
なぜ教育機関で働きたいと思うようになったのか。
ここが軸です!
「なぜ教育機関で働きたいのか」のヒントとなるトピックを集めた記事がこちらです。
以上、ここまで7個の「大学職員の面接に落ちる理由」を挙げてきました。
この時点で4つ以上当てはまっていれば、
「落とし穴に気付けたことが幸い」と前向きに考えてくださいね!
落ちる理由【8】面接時に先に座ってしまう応募者
続いては、テクニック的な側面の「落ちる理由」を挙げていきます。
完璧なマナーで面接にのぞむ

面接会場で自分の順番がきたら、
- まずノックはコンコンコン、と3回が正しいマナーです(2回はトイレ個室のノック)。
- 部屋の中から「どうぞ」と促されてから入室します。
- 入室後はフルネームで名乗り「よろしくお願いします」程度の軽い挨拶。
- 面接官が「どうぞおかけください」と言うまでは、自分から座ったり荷物を置いたりしません。
この程度の「超」が付く基本ができない応募者が7割ほどいます。
マナー不足の失敗例
面接会場で順番がきたら、
- そのままドアを開けて入室し、
- お辞儀さえなくそのまま椅子まで歩き始め、
- 何も促されていないのに椅子に座ってしまう、
さすがに中途採用でこのパターンは即アウトです。
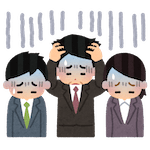
基本事項を完璧におさえよう!
社会経験がある以上、「常識レベル」のビジネスマナーは「完璧に」身に付けて臨んで下さい。
再度繰り返します。
本番前に基本事項を高レベルで準備しておくことが職員の適性です。
落ちる理由【9】「。」がない話し方をする応募者
話し方一つとっても、簡単に合否の分かれ目になります。
結論と起承転結を意識しよう

意気込み過ぎていて何を言っているのかわからない人も多いです。
言いたいことがあり過ぎて話が長くなりがちな応募者も多いです。
結論から答えて、そして起承転結のある話し方を徹底しましょう。
具体例
例えば、ある質問に対する答え方として、
「はい、おっしゃるとおりです。」
⬇︎
「と言いますのも〜だからです。」
⬇︎
「例えば〜についても同じようなことが言えると思います。」
⬇︎
「ですので〜だと思います。」
といった話し方の骨組みがあれば、聞いていて安心感を感じます。
職員には説明力が必要
「。」のある話し方、そして適切な「接続詞」でつなげば、起承転結のある話し方ができますね。
職員は、会議の場では質問を受ける立場です。

簡潔で的を得た事務局答弁が常に求められています。
落ちる理由【10】「戸締め言葉」を多用する応募者
「面接に落ちる理由」の最後です。
面接官への印象付け
「戸締め言葉」とは、何かと無駄に

「いや、」
を冒頭につけて話し始めるクセですね。
このクセは、聞き手側にネガティブな印象を与えてしまいます。
このような職員ウケしない言葉遣いには気を配っておいた方が無難です。
特に最終面接(役員面接)では、マイナスイメージにつながりやすいです。

その他の具体例
例えば、
「あ、そうですそうです。」
とか、
「あ、違います違います。」
といったリピート言葉。
これは未熟な印象につながります。
「〜〜というか、、そうですね、そんな感じです。」
といった新卒学生ようなコメントの終え方。
どれも中途採用レベルだとイタいですね。
無意識に使ってしまっている職員ウケしない言動。
十分な対策を練っておいた方がいいと思います。
この辺りが重要な理由は、
自分では「全く」気付かないからです。
対策方法
逆に考えれば、話し方のクセを正して、それを改善できれば、
それだけで印象が180度変わります。
模擬面接などで、ぜひトレーニングしておきましょう。
大学職員の面接に落ちる理由【まとめ】
以上、合格には程遠いタイプの典型例を例示しました。
大体7割くらいの応募者は、こんな感じで門前払いです。
ここまで読んで、気付いた人も多いと思います。
大学職員の面接対策はそれほど難しくありません。
理由は、
上記と逆のことをやればいいだけだからです。
確かに事前準備は大変ですが、やり方さえ間違えなければ、割とスムーズに内定に届くはずです。
その「やり方」を、以下の記事で全て公開していますので、ぜひ役立てて下さい!
似たような視点で、別の切り口から面接対策を分析した記事がこちらです。
具体的な方法でテクニックを磨いておきたい人はこちらが参考になります。
以上です!
「リクナビNext」で求人情報を調べる時は、
で検索しましょう!
おさらいはこちら
- 大学職員の面接に落ちる理由を失敗例でケーススタディしよう
- 落ちる理由【1】学長名を知らない応募者
- 落ちる理由【2】「大学」と「学校法人」の違いがわかっていない応募者
- 落ちる理由【3】「学生のために」というフレーズを使う応募者
- 落ちる理由【4】カウンター越しに見えるスタッフのことを職員だと思っている応募者
- 落ちる理由【5】職員の仕事をデスクワーク中心だと思っている応募者
- 落ちる理由【6】「新しい提案をしたい」というフレーズを使う応募者
- 落ちる理由【7】ネガティブ応募
- 落ちる理由【8】面接時に先に座ってしまう応募者
- 落ちる理由【9】「。」がない話し方をする応募者
- 落ちる理由【10】「戸締め言葉」を多用する応募者
- 大学職員の面接に落ちる理由【まとめ】
その他、以下のメニューで体験談を数多く語っているので転職活動の参考にしてください!