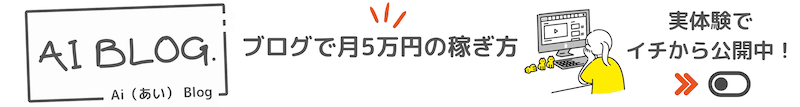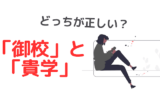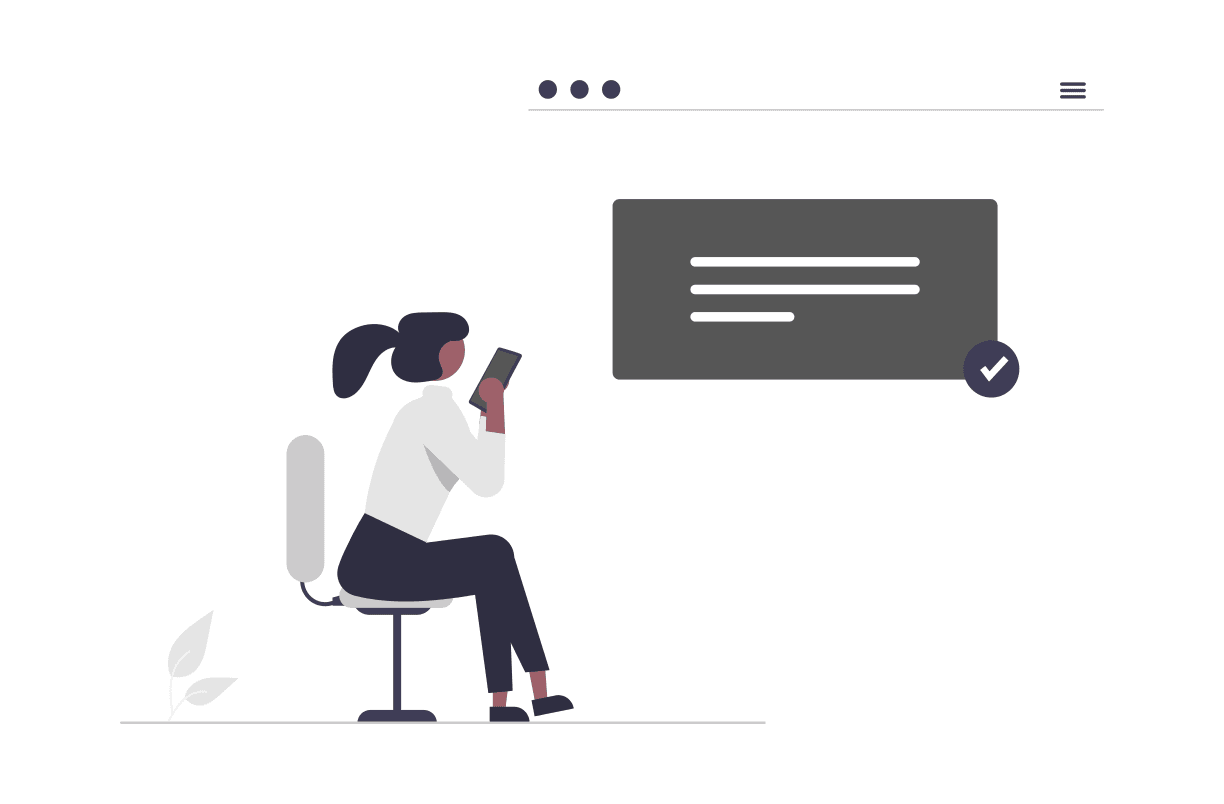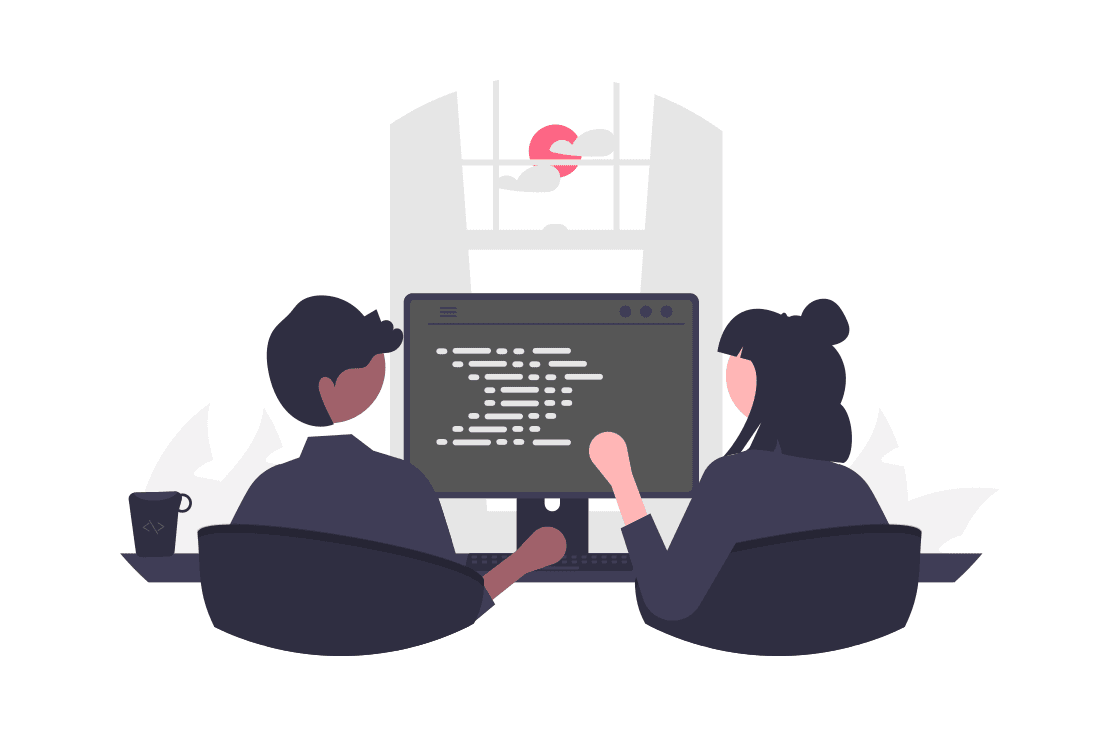大学職員の採用面接で、逆質問をする「オーソドックスな方法」を覚えておきましょう。
柱となるポイントは、
- 絶対に質問すること
- 万能フレーズを用意しておくこと
- 最終面接では使わないこと
です。
順を追って見ていきましょう!
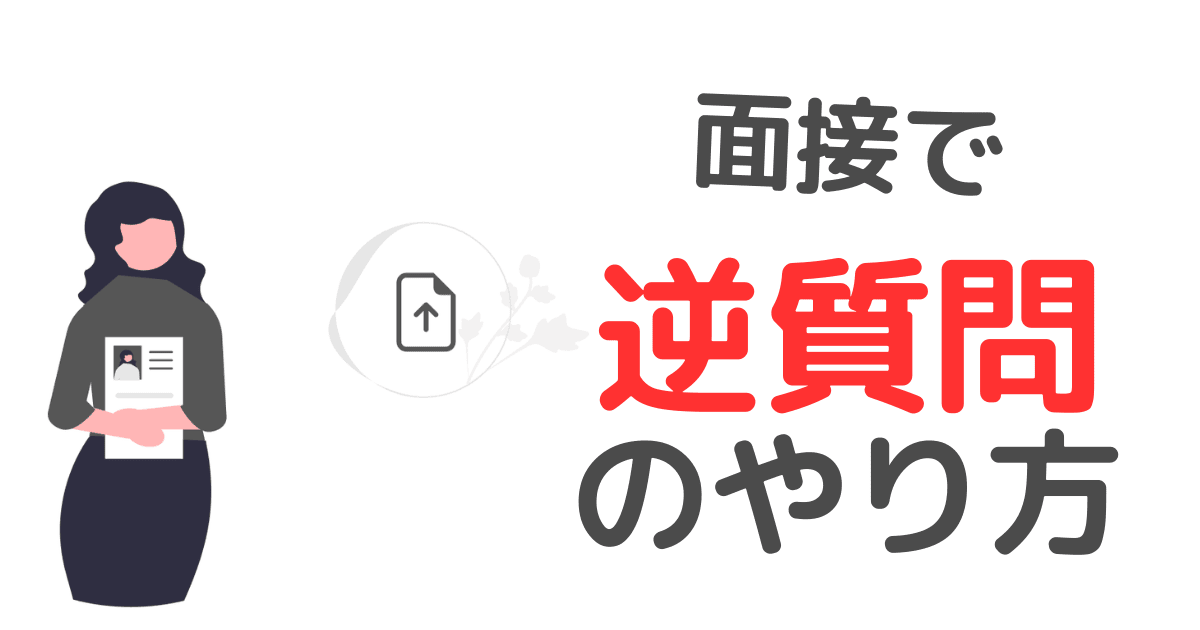
元大学職員のAI(あい)です!教務、国際、研究支援、経理、人事、学長室、と経験して20数年。早期退職を利用して引退。大学職員としての経験談をPR記事として公開中!
「最後に何かありますか?」からの逆質問
面接の際「最後に何かありますか?」といったシチュエーションは結構な確率であると思います。
この状況では、
「絶対に」何か言うべきです!
例えば、
(応募者)「いえ、特に大丈夫です」
などとサラっと終わってしまう応募者については、
(面接官)「本気でウチで働きたいと思ってるのかな、、」
といったネガティブ印象で面接が終わってしまいます。
逆質問における面接官心理を把握しよう
面接直後は、面接官同士で、まずは印象面で合否判定をすり合わせます。
しかし、そんなすり合わせもわずか数分。
その後、続々と別の十数人と面接を重ねていくのが面接の実態です。
1日の面接が終わって十数人を振り返ったときは、ほとんど印象が残っていない応募者が普通に何人もいます。
面接の終わり方が薄口の印象だと、ほぼ間違いなく「印象に残らない」グループに入ってしまいます。
とにかく理屈として、
「最後に何か自分から質問をした方が有利である」
と決め事を作っておくことが、面接通過のキモです。
逆質問の効果
このように、逆質問の効果はまさに、
面接の終わり方は極めて重要ポイントだから。
この1点につきます。
逆に面接途中の段階なら、そこまで深刻に対策をとる必要はありません。
例えば、
(面接官)「ここまでで何か質問はありますか?」
といったシチュエーションなら、感じ良く受け流すか、自然に出てくる質問をしておけばOKです。
では、どんなことを逆質問すればいいのでしょう。
そこを見ていきましょう。
逆質問の具体例
逆質問の具体的対策がこちらです。
- 特徴的なフレーズを予習しておく
- 面接官に経験談を話させる
- 万能フレーズを用意しておく
順に説明します。
特徴的なフレーズを予習しておく
まずは、応募先の大学について具体的なフレーズを使って質問をするやり方です。
あらかじめ予習し、正確に記憶しておくだけで「それっぽい」対応ができるのでおすすめです。
(応募者)「御校は、20●●年に●●学部を新設されましたが、その際は職員にはどんな苦労があったのでしょうか。」
(応募者)「御校には、●●キャンパスと●●キャンパスがありますが、キャンパスによって仕事の進め方は異なりますか。」
(応募者)「御校は、受験者数が●万人に伸びましたが、職員はどんなところで影響力を出しているのでしょうか。」
この逆質問のやり方は、きっちりと準備をして本番に臨んでいる姿勢をPRできます。
まさに大学職員の適性としてストライクの姿勢なので、好印象に繋がりやすいですよ。
しかも、面接の最後で好印象の空気が作れるので、かなり有利に傾きます。
面接官に経験談を話させる
2つ目は、面接官に経験談を話させるやり方です。
コツは、面接途中で、面接官自身の仕事経歴がコメントされた時は、それを覚えておくこと。
(応募者)「先ほど、国際課の業務は意外と地味だと伺いましたが、例えば国際協定を締結する時などは、職員はどんなところで苦労していますか。」
(応募者)「広報部での経験があると伺いましたが、広報部は華やかなイメージがありますが、不祥事対応などの時は、職員はどのように対応しているのでしょうか。」
勤務経験があると、面接官はそこでの苦労話や武勇伝を気持ちよく話してくれます。
結果、自然体で有意義な対話の空気感ができ、良い空気感で面接が終わります。
万能フレーズを用意しておく
一口に逆質問と言っても、どんな風に振られてくるのかは未知数です。
そのため、どんな時でも対応できる万能フレーズを用意しておくのがおすすめです。
(面接官)「最後に、何か質問はありますか?」
(応募者)「はい・・あの・・質問ではなくて申し訳ないのですが〜」
と、一言付け加えると、その後は、どんな内容にも変換できます。
言い残した志望動機や自己PRなどにも話を転換できます。
また、
(応募者)「繰り返しになって申し訳ないのですが〜」
といったフレーズなどは、逆質問ネタをド忘れした時などに使えます。
面接途中で、上手く伝わらなかったやり取りを、再度補足したりもできます。
その他、
(応募者)「質問は特にありませんが、本日は大変勉強になりました。〜」
と、感謝や感想を述べて、「⚫️大学で働きたいという気持ちが、さらに強くなりました。」と志望する気持ちを上手く織り込むのもありです。
面接の印象は、最後の部分が大きなウェイトを占めています。
これらの例は、その点にターゲットを当てた、面接テクニックの黄金セオリーです。
逆質問の注意点-1
上手く使えれば面接をいい雰囲気で終わらせられる逆質問。
注意点もおさえておきましょう。
注意点は、
役員面接で使うのはNG
という点です。
役員面接は、たいてい最終面接。
この段階では、あなたは大学職員としての合格ラインに既に達している状態です。
そして役員面接は、実質的には「面談」としての位置付けが通常。
その「面談」では、聞かれたことに対して、端的に、かつ、笑顔で答えておけば十分です。
つまり、プラス評価は不要で、マイナス評価さえされなければOK。
下手に逆質問をして、かえって変な印象を持たれるリスクは避ける方が無難です。
逆質問の注意点-2
ありがちな失敗例がこちらです。
質問をあらかじめ熟考しすぎて、
本番でクドいコメントのようになってしまうとNGです。
準備しすぎた内容であるがゆえに、いざ本番ではクドい感じの内容や話し方になってしまって、聞いている方としては、
(面接官)「結局何が聞きたいの?」
とか。
その状況に陥り、自分自身がパニックになってしまう応募者もいたりします。
これでは完全に逆効果です。
コツは、セリフとして記憶するのではなく、重要フレーズだけ覚えておく、といった感じです。
実戦形式のケーススタディ、例えば模擬面接などが最も有効でしょう。
大学職員の面接で逆質問をする方法【まとめ】
逆質問については、
準備しておかない理由がありません。
最低限のテクニックであり、同時に上級のテクニックでもあるので、迷うことなく磨いておきましょう。
以上です!
「リクナビNext」で求人検索する時は、「学校法人 大学 専任職員」で検索しましょう!
この記事が参考になった人なら、以下の記事もピッタリなはず!
大学職員の書類選考や一次面接は、コツを知らなければ連戦連敗が続きます。要領よく対策したい人はぜひ参考にして下さい。
面接でよくある質問。こんな時はどう答えるのが正解なのでしょうか?
その他、大学職員への転職コンテンツを以下で充実させています。ぜひ役立てて下さい!