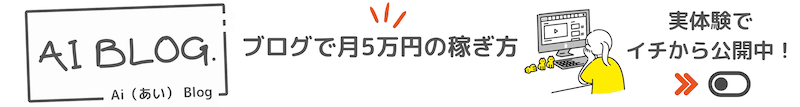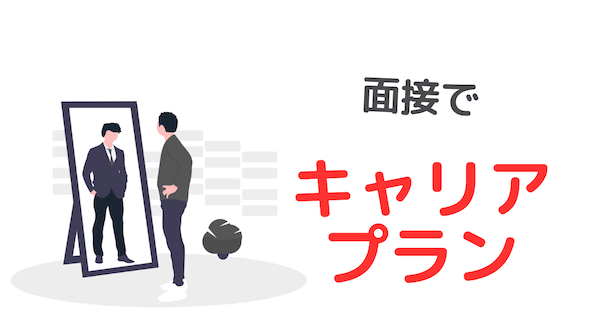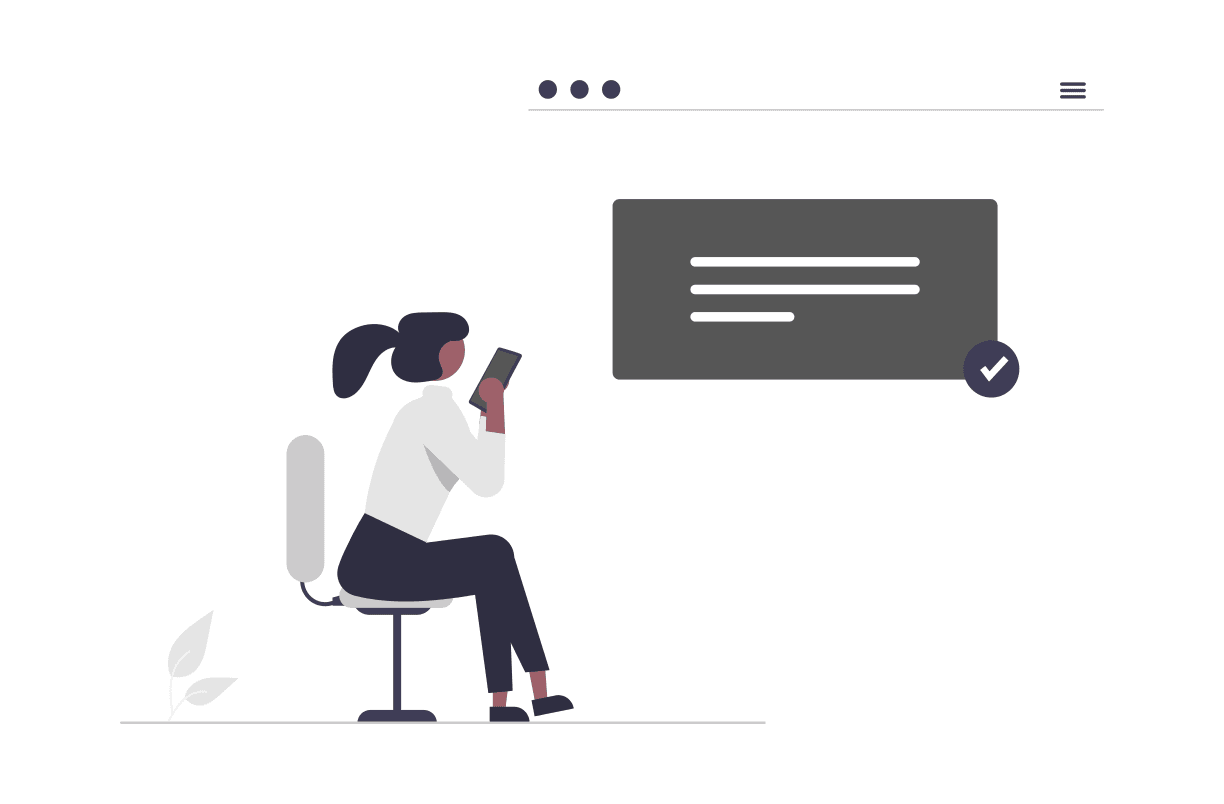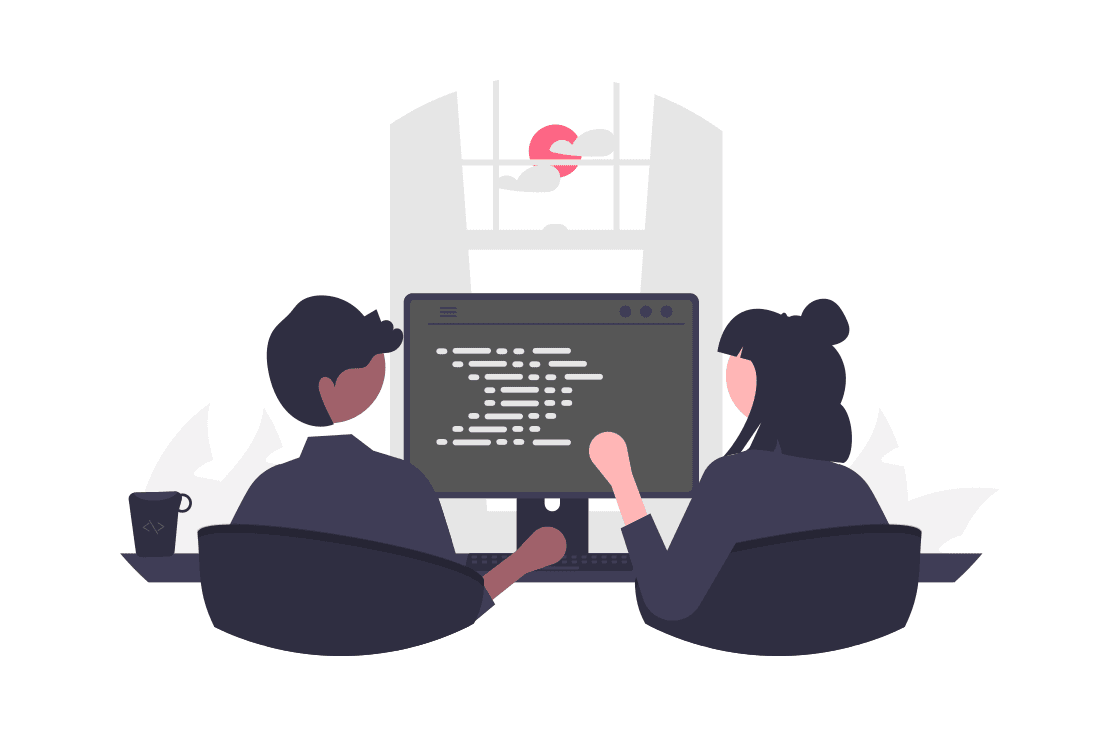(面接官)「職員に採用されたら、どんなキャリアプランを目指していますか?」
この質問、内定者たちはどんな風に答えているのでしょう?
この記事はそんな疑問にお答えできます!
内定に直結するトピックだけでまとめていきます!

元大学職員のAI(あい)です!教務、国際、研究支援、経理、人事、学長室、と経験して20数年。早期退職を利用して引退。大学職員としての経験談をPR記事として公開中!
大学職員のキャリアプラン【その1】「教学系部門」を経験する
まずは一つ目の柱の理解から。
教学系とは
一つ目は「教学系」という考え方を理解することから始めましょう。
「教学」とは、大学を「教育機関」として見たときの呼び方です。
このあと説明する様々な大学の側面の中で、最も馴染みやすい視点だと思います。
※その他の柱は「法人系」と「研究系」。順に紹介していきます。
教学系の具体例
大学を教学系として見た場合の具体例は、
- 教務部や学生部
- 奨学金や国際課
- キャリアセンター
などのことです。
あとは「入試課」も教学系の機関です。
教学系は学校業務のキャリアプラン
教学系では、高等教育機関としての「学校」で業務を日々行います。
ここの部門を経験することで、
学生の「学び舎」としての学校=大学
これが、どのように運営されているのかが深く理解できるようになります。
大学の目的は学位授与
あらためて、
(面接官)「大学ってどんなところだと思いますか?」
などと面接で聞かれた場合などは、以下のように理解しておくとよいでしょう。
大学の本流は「正課」
大学の究極目的は「学位授与」。
入学→履修→定期試験→単位認定→進級→学位授与(卒業)
これが基本の流れ。
これを「正課」と呼んだりします。
正課をサポートする「課外」
その究極目的の周辺に「課外」と呼ばれるものが位置付けられます。
「課外」の例としては、
奨学金や留学、サークル・体育会、就職活動
などがありますね。
「正課」が大学の究極目的。
そして学生の人間的成長を、
「課外」を通して側面からサポートする、
というのが大学の基本構造です。
このフレームを、全てにおいて完璧に事務運営するのが大学職員の役割です。
フレーズ的には、
学位を出すための組織運営
と言ったりします。
※ここは面接で使えるフレーズ!
この流れを、制度や理念に当てはめて事務運営していくうちに、高等教育機関の存在意義を深く理解できるようになります。
教学系は社会の動きと連動
教学系では、文科省など、国とも密接に絡んで仕事をすることになります。
この経験は「社会的に」大学の位置付けを色々と見られるようになります。
教学事務の例
例えば、日本も欧米のように「学費無償化」という流れがありました。
この場合、
- まずはマスコミや世論の動きが出始め(「日本の教育費は高過ぎるのでは?」という世論)、
- それが与党の議論へとつながり、
- そして立法へ向けたロビイングが行われ、
- 行政機関(文科省)が具体案を作り(学費無償化の案)、
- その案の妥当性を各大学長が意見し、、、
といったことに、教学事務という仕事を通して密接に触れることになります。
この場合の「教学事務」とは、例えば各大学の授業料推移やデータ収集、学生数や教員数との相関性、海外大学に出張して情報交換などまで行います。
教育を担う大学が、社会にとって重要な位置付けであることがイヤでも実感できるようになります。
以上が「教学系部門」のキャリアパスです。
続いては二つ目の柱、「法人系部門」を見ていきましょう。
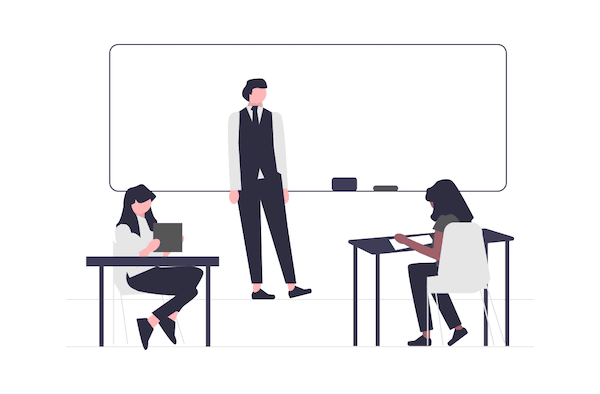
大学職員のキャリアプラン【その2】「法人系部門」を経験する
人事や総務や管財、経理、広報、寄付金室などが法人系の部門です。
法人系とは
法人系では、学生や教員や卒業生といった視点ではなく、
よく言う、
「ヒト」「モノ」「カネ」
の角度から「学校法人」を動かす経験を積めます。
法人系のキャリアプラン
法人部門を経験することで、
「私立学校法」
などという「学校法人」が社会活動するための
「根拠法」
などにも触れることになります。
企業的なキャリア
いわゆる「大学=学校」という視点ではなく、
「大学=組織」つまり「大学=法人」
として、企業的な視点でキャリアを積めるようになります。
法人業務の具体例
法人系の具体的は、
- 人を雇い、
- 賃金を払い、
- 収益計算をし、
- 不動産を取得し、
- 遵法行為をしながら、
- ブランディング活動をし、
- 企業価値を高める、
といった経験が積めるイメージです。
私立学校法
学校法人は、利益を生み出すといった目的は持っていません。
そうではなく、学校法人は、
「永続的に存在しなくてはならない」
という使命が、私立学校法の前文に明文化されています。
利益を目的にしない理由
その理由は、
扱っているものが教育だからです。
人生の重要なステージとなる大学が、流行り廃りや、景気の影響を受けるようでは、国民の不安感情を煽ってしまうことになりかねません。
※ここは面接で使えるフレーズ!
なので、非常に厳密な管理運営が求められていることが大きな特徴。
私立学校も国民負担で成り立っている
また、私立大学といえども、毎年、数億円単位の公金が投入されています。
さらに、学校法人は、納めるべき税金が数十億円単位で「少ない」ので、間接的な利益を得ているとも言えます。
このように、大学は他の企業などと比べて、かなり厳格に事務運営がなされることが求められています。
※そのため、どうしても保守的な組織文化になりがちな点がデメリットでもあります。
続いて3つ目の柱、「研究支援部門」です。
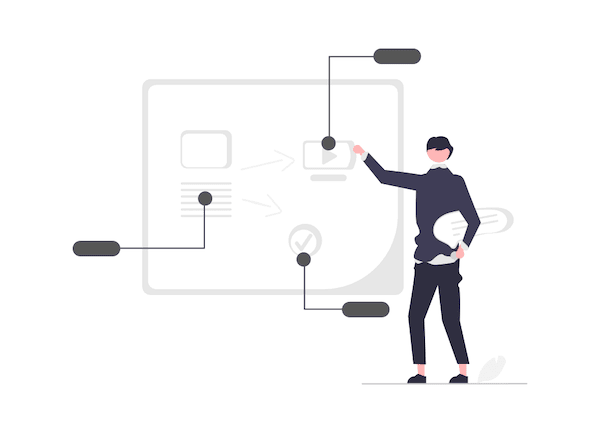
大学職員のキャリアプラン【その3】「研究支援系部門」を経験する
研究支援系の部門は、教員の研究活動をサポートする部門です。
研究支援とは
- 良い「教育」を提供するためには、
- 良い「研究」がその大前提になります。
- そして良い「研究成果」を出すためには、
- 良い「研究環境」が必須です。
※面接フレーズ!さりげなく使いましょう!
つまり、研究設備を整えたり、研究補助員を雇ったり、海外で学会発表したり、研究活動は幅広くカバーする必要があります。
それを事務サポートする部門が研究支援部門の仕事です。
※大学の中では、かなり本流の事務部門です。
研究機関としての大学
大学は「教育機関」であるとともに、「研究機関」でもあります。
※この二つは、似て非なる、全く別の概念!
大袈裟な話ではなく、研究があるからこそ、人類の進歩があるわけですね。
インターネットも、iPS細胞も、歴史研究も比較文化論も、全て研究が生み出したものです。
研究力の重要性
その研究の重要性は、近年さらに注目されています。
研究力と世界大学ランキング
例えば「世界大学ランキング」は、この研究力の指標が強い大学ほど、
というか、研究力の強い大学だけが上位に上がってきます。
大学は教育力よりも研究力
世界大学ランキンでは、医学、薬学、科学、工学、化学など、理系の大学が圧倒的に強いのが実態。
言い換えると、昨今の大学の本質的な評価は、教育力よりも研究力にあると言っても過言ではありません。
研究支援系のキャリアプラン
そんな「研究機関」としての大学がどのように活動しているのかが、研究支援部門で働くことで見えてきます。
- どんな研究に、いくら補助金が国から出されるのか。
- どんな海外研究者が、どんな研究で迎え入れられているのか。
- どんな研究に、どんな企業から共同研究の申し入れがきているのか。
そんなことを通して、研究機関としての大学の実情が読み取れるようになります。
※キーワードは「研究資金」「論文数」「学会」といった感じです。
以上が研究支援系についてでした。
次は全私立大学のうち、32校もある、医学部を持つ大学でのキャリアプランです。
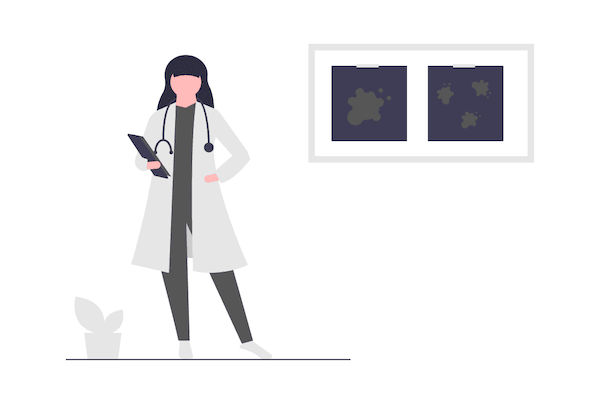
大学職員のキャリアプラン【その4】医学部・病院を経験する(医学部がある大学の場合)
医療もまた、人類社会に強烈なインパクトを与える存在であることは明らかです。
医学部・病院がある大学なら、そこで勤務することで、医療そのものの世界観を詳細に知ることができます。
医療先進国の中心地
臨床の現場だけではなく、制度としての医療の世界をも垣間見ることができます。
その理由は、
全ての大学は(大学病院は)「高度医療機関」と位置付けられているから。
つまり、単なる病院とは異なるわけです。
日々の仕事が、医療先進国として日本の医療政策にまで関わることになります。
※ここも面接で使えるフレーズ!
医学部におけるキャリアプラン
このような経験とともに、研究者でもあり、医師でもある教員と日々関わることで、大学の重要な側面を経験できるキャリアプランとなり得ます。
大学の中で医学部が与える影響力はとてつもなく大きいもの。
大学を知る上で重要なキャリア資産となります。
大学職員のキャリアプラン【その5】ジョブローテーション
以上のような切り口で、大学職員は3〜5年ごとに人事異動を繰り返して、それぞれの部門を横断的に渡り歩きます。
渡り歩いた結果、気がつけば大学のことが俯瞰して見れるようになり、ひいては日本全体の教育・研究・医療の状況を吸収することになります。
複数の柱の経験が重要
逆に、2〜3箇所だけの部署経験だと、実質的にはほぼ何も理解できていない状況に等しいです。
面接時のポイント
面接では、特定の領域を希望するのではなく、
「部門を跨って広く色々な経験をしてキャリアを積みたい」
といったコメントをすれば、大学のことをよくわかっているといった印象を与えられるでしょう。
その際、上記に説明してきた具体的なキラーフレーズを入れることがポイントです。
以上です!
ツールを使おう
この記事のような情報をもっとたくさん入手できれば、転職活動は上手くいくはずです。
「リクナビNext」で求人検索する時は、「学校法人 大学 専任職員」で検索しましょう!
その他の参考記事
以下の切り口の記事もきっと役に立つと思います。
志望動機のテクニックを、面接官側の視点で分析した記事がこちらです。
面接官も読んでいる「定番の本」を知りたい人はこちら。面接ネタをたくさんストックできますよ。
その他、目的別に以下のメニューからどうぞ!役立つ記事を連載しています!