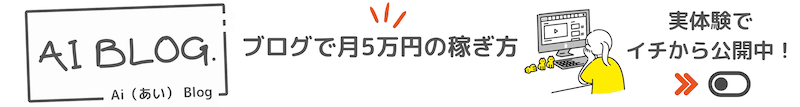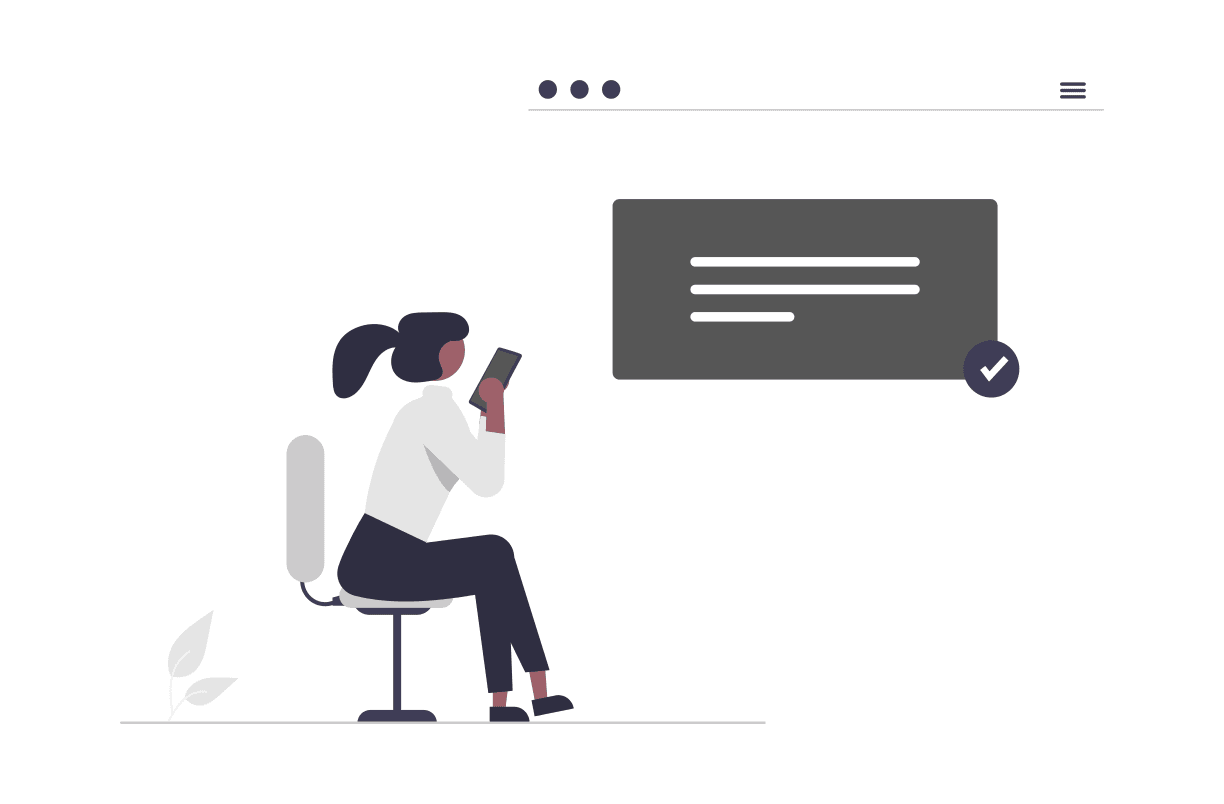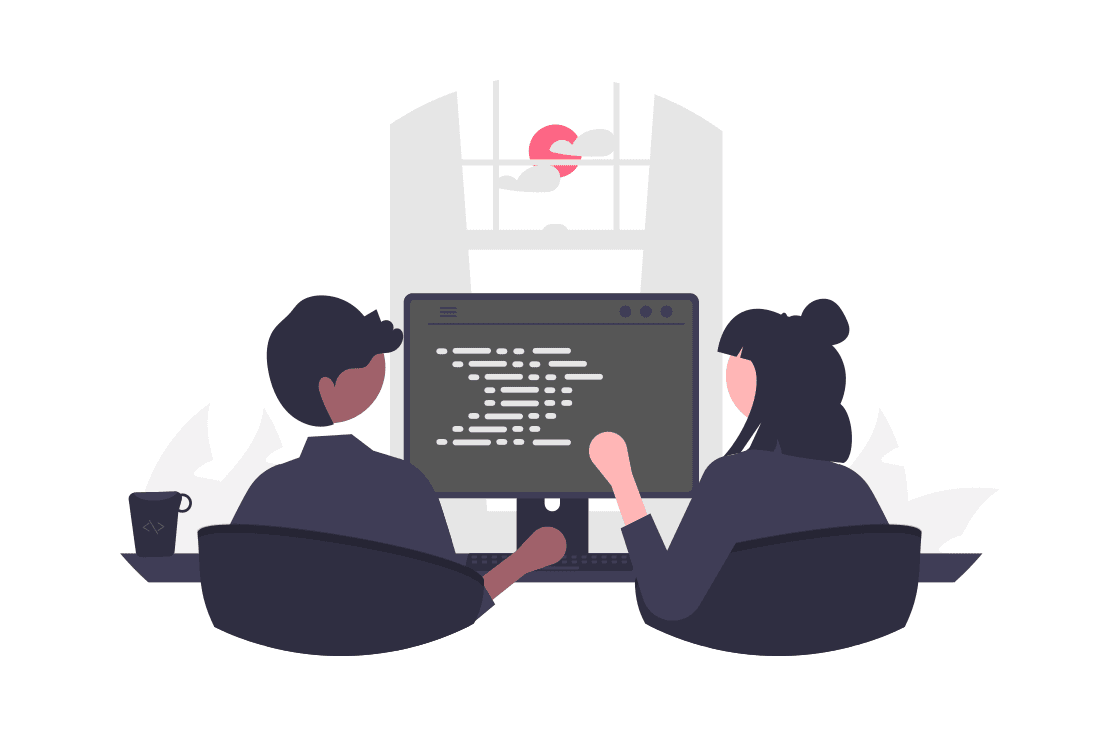今回の記事は、大学職員の国際交流の仕事内容について!
例えばこんなことを聞いてみたくないですか?
- 語学力はどこまで必要?
- 海外出張はどれくらいある?
- 周りの職員はどんなキャリア?
その他、
- TOEICのスコアどれくらい必要?
- 希望すれば配属されるの?
- 海外オフィスでの勤務の状況は?
などなど、この記事は、そんな疑問にお答えできます。
国際企画や国際戦略系の仕事経験も紹介します。
そして皆さんに気を付けて欲しい落とし穴、
「大学の国際化に貢献したいです!」
という面接でのアピールが、面接官にネガティブな印象を与えていることも、この記事を通して理解してください!

元大学職員のAI(あい)です!教務、国際、研究支援、経理、人事、学長室、と経験して20数年。早期退職を利用して引退。大学職員としての経験談をPR記事として公開中!
まずは、かなりオーソドックスな話題からいきます。
大学職員の国際交流の仕事内容
大学の中で国際案件を取り扱うのが国際交流課。
部署名は大学によって様々です。
- 国際課
- 国際センター
- 国際交流課
などが一般的な呼び方。
面接時には、その大学での「正式な部署名」でコメントすることが必須マナーです。
万一、ド忘れした場合は「国際関係の部署」など、遠回しに表現すれば致命傷は負わないでしょう。
※この記事では「国際交流課」という表現で統一します。
国際交流課の仕事内容
国際交流課の業務を簡単に表現すると、
「留学生の受け入れと送り出しの事務」
をメインに行う部署になります。
具体的にみていきましょう。
外国人留学生の受け入れ業務
外国人留学生の受け入れにあたっては、大学には細かな裏方業務が発生します。
例えば、
- 在留資格申請
- 寮の手配
- 来日時のオリエンテーション実施
- 来日後の学籍管理(履修・試験・進級など)
- 日本滞在中の全般的なカウンセリング
などがメイン業務。
その業務の背景には、
- 留学生の不安を取り除き、安心して自分の大学で学んでもらうこと
- 送り出してくれた派遣元の大学にも良い印象を維持してもらうこと
この2つがあり、それを念頭においた、レベルの高い事務ワークが求められます。
基本的には英語を使った業務が中心になります。
とはいえ、求められる英語レベルは、それほど高度なスキルは要求されません。
会話、メールで確実にコミュニケーションが取れる程度のレベルがあれば大丈夫です。
「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」といったコアな部分でミスがなければOKなレベル感。
TOEIC L&Rスコアで650点あればそこそこやっていける感じです。
在学生の送り出し業務
逆に、在学生を留学先に送り出す仕事では、上記のことを逆の立場で行うことになります。
そのため、留学先となる相手大学の国際部スタッフと、英語によるやりとりが発生します。
受け入れ・送り出しのどちらにも当てはまりますが、この仕事に求められる能力は、英語力というよりも、どちらかと言うとスケジュール管理や調整などの事務力です。
いかに英語力や国際感覚を備えた人材であったとしても、綿密な事務スキルがないと職員としては使い物になりません。
採用面接では、この点を十分に理解して面接官との会話に臨みましょう。
国際交流課のその他の業務
国際交流課のその他の主な業務としては、
- 留学に関する募集要項やHPの作成
- 大学間協定の実務調整
- 外国人講師の受け入れ調整
- 短期留学プログラムの実務調整
などがあります。
1.や2.の業務については「正しい英語」を使えるスキルも求められます。
海外出張
4.では、海外大学の附属語学スクールや、サマープログラムの実務にあたります。
サマープログラムなどの担当になると、実際にそのプログラムに同行することが多いです。
現地での業務は、プログラムの行程管理や学生の安全管理などがメイン業務。
年に1〜2回、学生に同行する海外出張といった感じです。
国際交流課の職員の特徴
国際交流課では、5割くらいの比率で、海外留学経験者やTOEICハイスコア(L&R900程度)の職員が国際交流課に配属される傾向があります。
近年の特徴は、その5割のうち、外国籍の専任職員が増えている点。
特に、中国籍の職員が多くなってきているのが目立ちます。
もちろん中国・台湾から来る留学生がダントツに多いからですね。
中国語でも安心して受け入れられる体制は、どこの大学でも課題になっています。
そして国際交流課の職員のうち残りの5割程度が、上記以外の一般的な大学職員。
つまり経理課や医学部や人事課など、普通に他部署から異動してきた職員などが半分程度います。
女性が多いのも特徴で、どこの大学でも全体の8〜9割が女性職員といった感じです。
様々な部署をジョブローテーションしてキャリアを積み上げるのが大学職員の組織文化です。
国際交流課もそのうちの一つという位置付けであることに変わりはありません。
希望すれば国際交流課に配属されるというわけではなく、人材育成や人事異動はあくまで組織の都合で実行されるのが一般的です。
ただし、帰国子女や国際経験豊かな人であれば国際交流課への配属可能性が高くなるのは事実ですが、その場合でも組織の理論が優先されることに変わりありません。
次は企画・戦略系の部署について。
国際戦略室や国際企画室などの仕事内容
次は国際戦略室や国際企画室などと呼ばれる部署の業務内容を見てみましょう。
これらの部署は同じ国際案件を取り扱う部署ですが、先に紹介した国際交流課とは違った役割を担う部署です。
具体的には、
- 学生(留学生)を相手にした仕事ではなく、
- 文部科学省との窓口業務を行ったり、
- 外国の大学と協定交渉や折衝をしたり、
といった業務をすることが多い部署です。
補助金申請業務
大学の国際化に向けて、国が多額の補助金を出すといった事業が多いのが、昨今の文部行政の傾向です。
その補助金を獲得できれば、その大学は国際化に向けてより一層の推進力がつくのはもちろんです。
※複数年に渡って数億円の資金援助が得られることも!
また、国の国際化事業に認定された大学となれば(補助金を勝ち取れば)、国内外へのPR価値も計りしれません。
ですので、国際化に関する補助金を獲得するために、どこの大学もかなりの事務エネルギーを注ぎ込んでいます。
そして、この補助金申請業務は、かなりハード・・・
具体例として、Web上に掲載されていた慶応大学の申請書、こんなのを作ったりするイメージです。
これを見ると一目瞭然ですね。
- データ収集力
- データ分析力
- 各分野に詳しい人たちと人脈があること
そういった能力がないと勤まらない仕事です。
国際連携業務
その他には、大学間での国際連携や国際協定を締結するなど、企画実行をする業務があります。
「年間2名までお互いの大学(学部)に交換留学生を送ることができる」
といったパターンが一つ。
※要するに「留学費用がかからない」という点が学生のメリットです。
または、
「2年間はこちらの経営学部で学び、残りの2年間をハーバードビジネススクールで学べば、両方の大学を卒業したことにする」
といった協定パターンも多いです。
後者の方が、いわゆる「ダブルディグリー」と呼ばれている協定です。
職員の具体的な動きは?
その協定締結に至るプロセスで、職員が関わるのはもちろん事務的な面だけ。
協定書の文書チェックや協定式の準備などが主な業務になります。
従って、職員は国際感覚を駆使して活躍しているというよりも、他の事務部門と同じように、事務作業をきっちりと実行できるといった、極めてオーソドックスな職員象が求められています。
海外出張
国際戦略室や国際企画室の海外出張の状況は担当業務によって異なります。
国際補助金申請業務を担当する場合などは、海外出張の機会は年に1回あるかないかといったところ。
海外出張するケースとしては、国際カンファレンスなどに参加して他大学職員との人脈構築や、情報収集にあたる感じです。
一方の国際協定を担当する部署では、現地の大学に、学長の秘書役として同行することが多く、頻繁に海外出張をすることになります。
世界中を飛び回っている感じの仕事です。
ちなみにこの業務は、日本語でも難しい、高度な交渉力や調整力を駆使した事務官としての動きが求められます。
例えば、世界の大学長たちと、英語でユーモアを交えながら、堂々と交渉を進められるような能力が必要。
食事会やレセプションなどに学長に同席して出席し、ゆっくりと相手の懐に入り込んで友好関係を構築していくニュアンスです。
どんな角度から質問が来ても、スパッと答えられる広く深い大学の経験と知識が必要です。
10年以上かけて大学内の様々な部署を経験し、それなりの役職(係長や課長クラス)になって初めて携われる業務です。
国際戦略室や国際企画室の職員の特徴
人数は数名程度、どこの大学も多くて5〜6名といったところです。
さらにそのうち、英語圏ネイティブの外国人職員が何名か所属していることも特徴です。
国際交流の仕事内容と採用面接
実際の採用面接との関係を具体的にみてみましょう。
国際交流の仕事を希望する応募者は多い
大学職員中途採用への応募者には、国際系の事務部門を志望する方は多いです。
そういった方々は仕事内容に華々しいイメージを持っていて、国際舞台で自分の語学力や留学経験を活かしたい、といったキラキラした夢物語を述べてくるのが多数派です。
残念ながらそのパターンの応募者は、面接官にはネガティブなイメージにつながりやすい傾向にあります。
理由は、あくまで裏方スタッフである大学職員の役割を履き違えてしまっているからです。
仕事のスタンスは他の部署と同じ
国際交流課も地味な繰り返し業務が多い大学事務の一つです。
つまり、人事課や管財課など他の部門と一緒です。
中途採用にもかかわらず、こういった認識違いのまま面接に臨むと、情報不足を露呈しているようなもの。
大学職員の採用では瞬殺されますので、十分認識しておきましょう。
面接時のポイント
では、面接では実際、どのような対応が求められるのか具体的にみてみましょう。
例えば、
「御校は、残念ながら文科省のスーパーグローバル事業は獲得できなかったようですが、ダブルディグリー協定が10件もあることをホームページで拝見しました。
それを見て、着々と国際化が進んでいるという印象を受けております。
そういった環境がさらに前進できるように、私の長所である裏方で堅実に力を発揮できる点を活かして、事務作業を通して国際交流課に配属された場合などでも貢献したいと思います。」
といった感じであれば、好印象です。
好印象の理由は、
- 具体的であり、
- その大学にしか通用しないコメントになっていて、
- かつ、職員の役割を理解できている
といった感じです。
国際交流に関わるその他の部署
大学の中での国際交流に関わるメインの部署は国際交流課と国際戦略課です。
とはいえ、その他に以下のような部署でも国際的な業務が行われていることが一般的です。
- 入試課
- 広報課
- 学長室
- 海外オフィス
それぞれ順を追ってみていきましょう。
入試課での国際交流業務
海外の外国人学生が、一般の入学試験を日本語で受けて、正規学生として入学するケースが増えてきました。
または、日本語ができなくても、英語だけで4年間を修了できる課程を持つ大学も増えてきました。
この流れは、この先、間違いなく加速していきます。
そうすると、入試課の業務もだんだんとグローバルになってきています。
入試実務で英語対応が増えることはもちろん、入試広報も全世界が対象になります。
職員が海外に出張して、大学説明会を開くことも頻繁に行われています。
広報課での国際交流業務
もはや大学広報の対象も国内だけではありません。
世界中に向けてPRし、全世界から優秀な学生を取り込む時代になっています。
そのため、国際交流課や入試課と連携して、ほぼ全ての大学が国際広報を強化しています。
必然的に、広報課の業務も国際色が強くなってくるのも肯けますね。
具体的には、英語版のホームページの運営はもちろん、英語によるSNSや動画配信などにも職員による事務フィールドが広がってきています。
学長室での国際交流業務
大学間の国際連携は、学長同士の人脈構築から話が始まり、トップダウンで実現することも少なくありません。
もしくは、国際担当理事と呼ばれる、執行部の国際担当責任者などが協定締結を牽引します。
そうすると、学長や理事は積極的に海外の学長会議やシンポジウムなどに出席して、コンソーシアムやアライアンスにメンバーとして加盟し、長い時間をかけて大学同士の信頼関係を築いていく行動が求められます。
そのような執行部の足元を支える業務を行っているのが学長室の職員。
- 海外コンソーシアムへの加盟交渉
- 海外からの学長訪問団の受け入れ対応
- 各国大使館との連携・調整
などなどが具体的な業務、もちろん全て英語です。
これからの時代は、学長室の仕事も、より一層世界に目を向けた動きが求められています。
海外オフィス勤務
例えば早稲田、慶応、立教などは、ヨーロッパや東南アジアの主要都市に現地オフィスを構えています。
当然、そこで働くのは人事異動によって転勤を命ぜられた職員です。
派遣される駐在員は、大体が1名。
中堅クラスの若手、といった感じの職員が多いです。
仕事内容は、ロンドンオフィスならそこを拠点にしてヨーロッパ中を駆け回り、大学の広報活動や、国際カンファレンスに大学代表として参加して情報収集をする感じです。
上海オフィス勤務なら、そこを拠点にして東南アジア全域を飛び回っています。
ビザの状況があるので、数年ごとに入れ替わり職員が派遣されています。
一概には言えませんが、こういった転勤には公募制を採用している大学が多いです。
自分から希望をして、学内選考に受かれば辞令が出る、といった感じです。
国際交流の仕事内容まとめ
以上、大学職員の国際交流の仕事内容だけを切り取ってみてきました。
おさえておきたいのは、大学職員のキャリアパスは、ジェネラリスト養成にあることが多い点です。
つまり、国際案件に特化したスペシャリスト職員を求める大学はそう多くはありません。
そのあたりを的確に認識した上で、他の仕事内容もよく把握して大学職員への転職活動に備えてください。
「ジェネラリスト養成」と言われてもピンとこない人には、以下の記事がおすすめです。
大学職員のキャリアパスを初心者向けに解説した記事です。
転職先として大学職員に興味を持った人は、以下のメニューで情報を発信しています。ぜひ役立てて下さい!