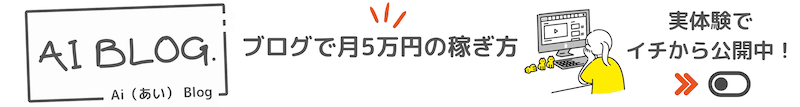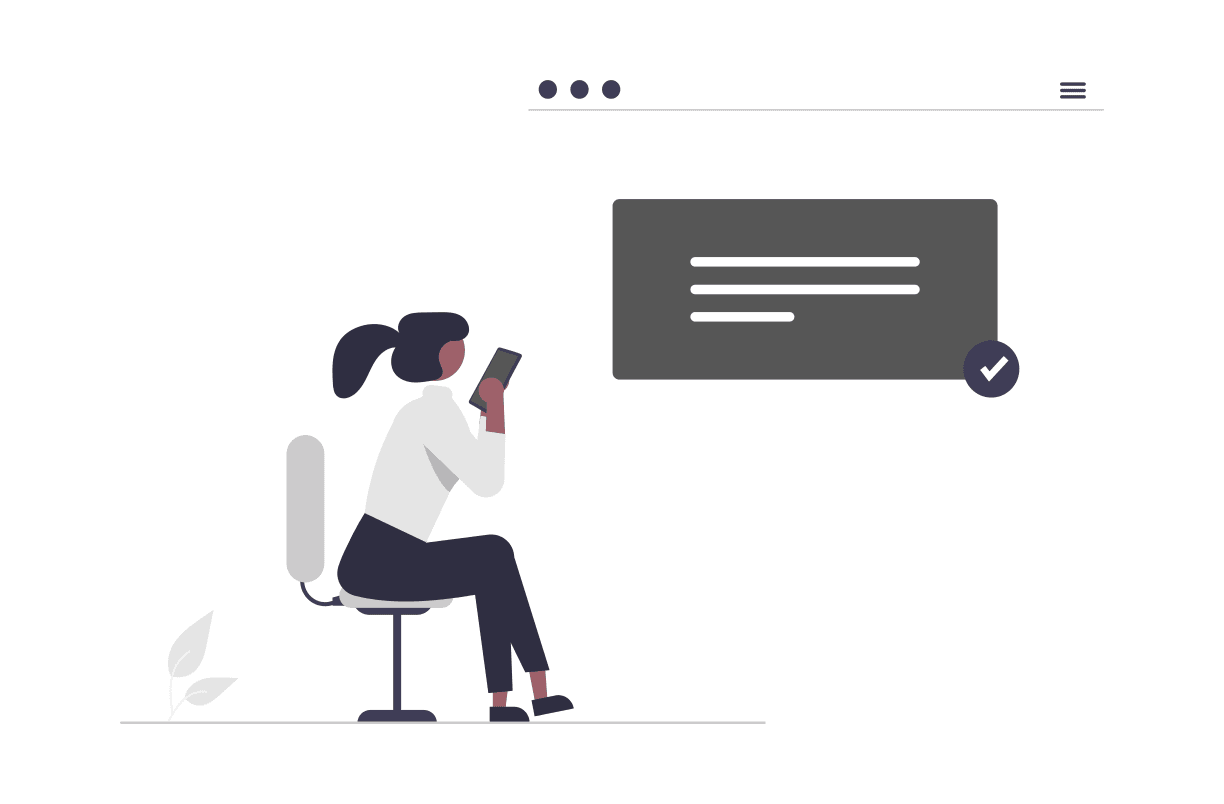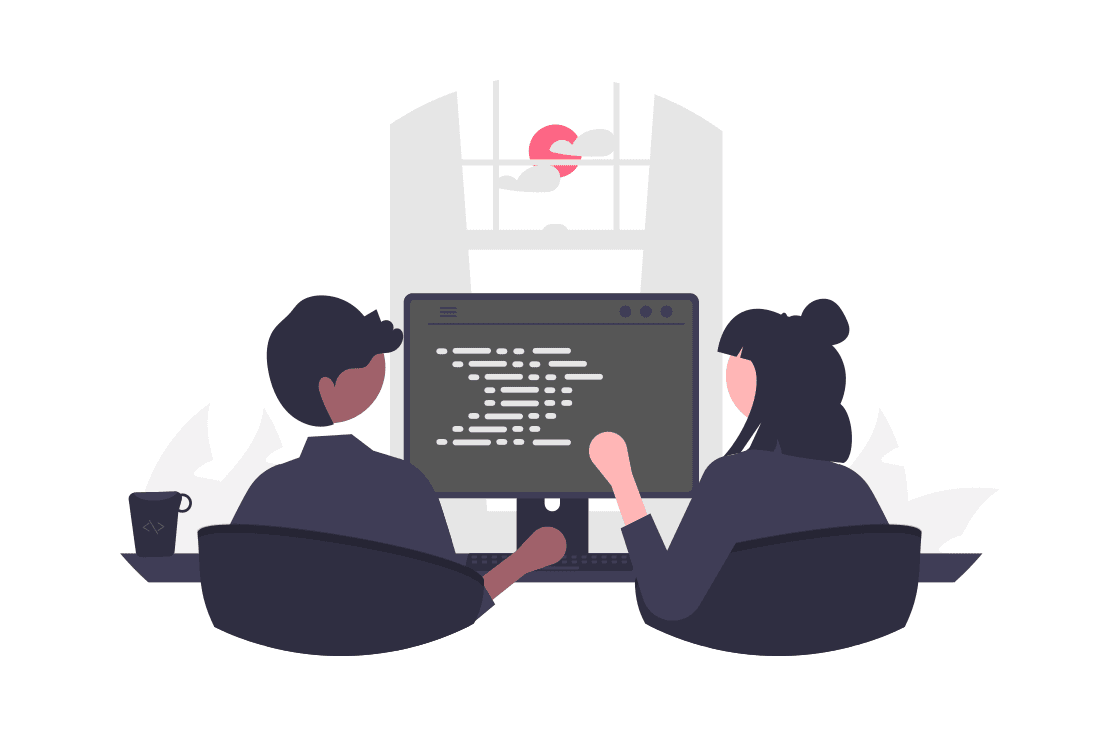この記事では、大学職員の主力部署、
- 総務部
- 人事部
- 経理部
このあたりの仕事内容を詳しくお届けします。
転職活動に役立つ視点で解説!
ぜひ参考にしてください!
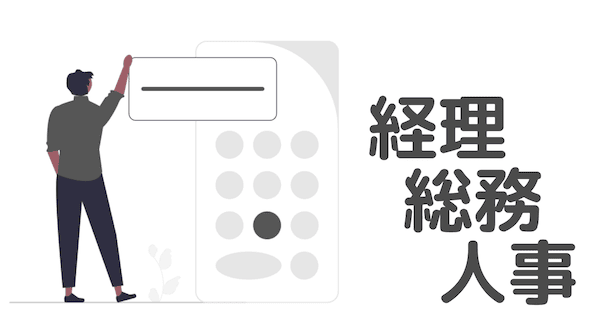
元大学職員のAI(あい)です!教務、国際、研究支援、経理、人事、学長室、と経験して20数年。早期退職を利用して引退。大学職員としての経験談をPR記事として公開中!
まずは総務部の仕事内容から。
大学職員【総務】の仕事内容
総務部の仕事は守備範囲が広く、つかみどころもない点が特徴です。
総務部の業務範囲は広い
総務という言葉が示す通り「総合的な事務」を扱っているからですね。
大学によっても、同じ総務部とはいえ、その業務フィールドが七変化するのが通常。
とはいえ、どの大学でも共通するコアな部分の仕事内容は、
- 役員会や理事会の運営
- 法人登記や行政申請の管理
- 定款や規程や学則などの管理
といったあたりです。
大学によっては、
- 危機管理対応(コロナ対策、震災対応など)
- 法律改正への対応
- 顧問弁護士事務所との連携業務
なども行っています。
さらに、
- 秘書業務
- 広報業務
- 卒業生や寄付金受付業務
などを総務部で行っている大学もあります。
■組織図に目を通しておこう■
面接前に組織図に目を通しておくと、面接への効果が出ますよ。
総務部を軸に置いて大学の組織を眺めると、その大学の事務運営の骨組みが理解できます。(早稲田大学の例(組織図))
この辺りを当然のように理解していたりすると、面接する立場としては、
「あ、わかってるねぇ(さすが中途採用)」
といった心理状況になり、印象も良くなります。
大学特有の総務部の業務
大学特有の総務部の業務内容といえば、式典の主催。
入学式や卒業式などの運営です。
多くの大学で、入学式や卒業式は、総務部が主要部署となって実施されています。
式典の運営
入学式や卒業式は、中堅以上の大学だと数万人単位の来場者を迎える一大イベントです。
規模感は、パシフィコ横浜や、さいたまスーパーアリーナの貸切レベル。
予算も1回で数千万円規模になるのが普通です。
総務部の職員は、イベント会社と運営調整を行ったり、式典の進行シナリオを作成したり、来賓のハイヤー手配や謝礼金や控室の準備などをします。
また、遠隔会場へのライブ中継の手配などもやらなくてはなりません。
都市部の大学なら、地方会場も借り切ったり、そこに大型スクリーンを複数個手配し、リハーサルを入念に行い、そして質の高いアーカイブが残せるように打ち合わせを繰り返したりします。
式典の本番
式典当日は、総務部スタッフが、
- 大会場で来場者の誘導をしたり
- 交通機関の乱れがあれば、スケジュール変更に対応したり
- 体調不良者が出たら保健室に連れて行って対応したり
などでバタついた、慌ただしい1日になります。
大学ではイベント対応の業務が多い
実は式典に限らず、また総務部に限らず、大学にはこういったイベントごとは結構あります。
例えば、
- 入試
- 学園祭
- オープンキャンパス
といったところが主なイベントのイメージ。
また、
- 様々な表彰式
- 著名人を招いての講演会
- 大学や学部の設立●●周年記念式典
などの運営も、100%職員が事務局です。
1年以上の準備期間を設けることも珍しくありません。
当然、イベント開催日が土日だったりすると、本番時の休日勤務が発生したりもします。
大学職員は事務作業だけではなく、各種催し事の現場要員としても重要な役割を担っています。
現場では、緊急対応でダッシュしたり、重い荷物を運んだり、大声を出して会場誘導にあたったり、といった業務もありますので、その点を理解して面接にのぞみましょう。
猛暑、積雪、台風などと重なると、結構大変です。
面接で、
「え、デスクワークだけじゃないんですか?」
といった反応を見せてしまってはNGです。
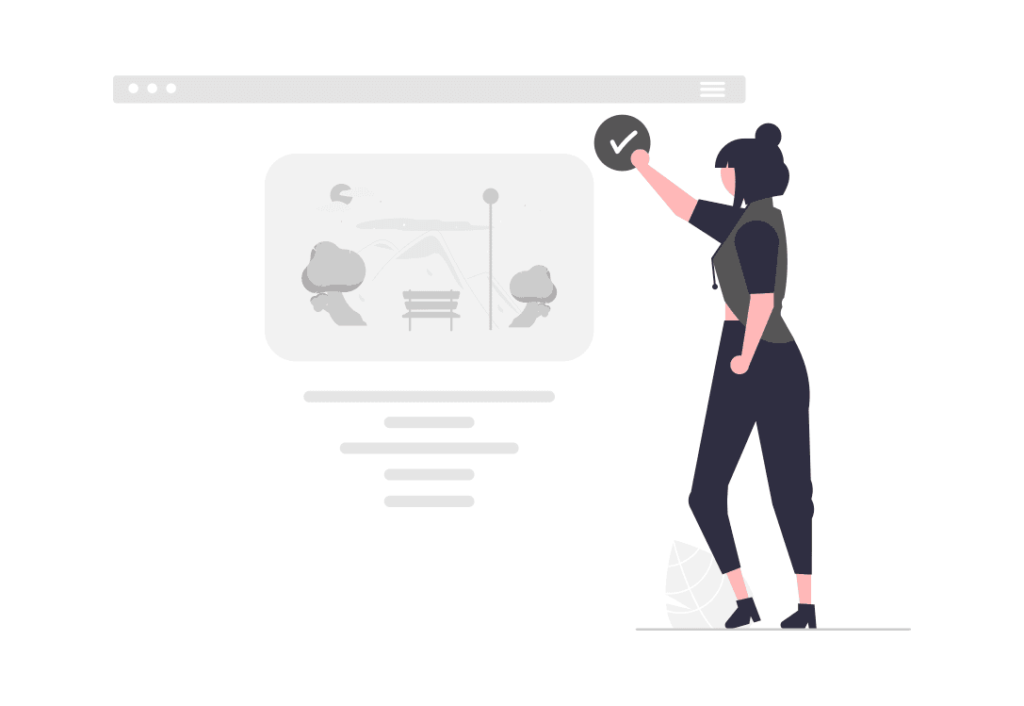
続いて、人事の仕事内容です。
大学職員【人事】の仕事内容
さて、管理部門の人事部の仕事内容について見ていきましょう。
民間企業と同じような仕事内容
人事部は、大学職員業務の中でも、本流の部署の一つと言えます。
やっていることや、部署としての重要度は民間企業と変わりないかもしれません。
- 職員執務評価の制度を設計したり、
- 人材育成の戦略を立案したり、
- 給与制度を整えたり、
と、「ヒト」を通して組織の骨組みを整える仕事ですね。
ですが、大学という教育・研究機関での制度設計です。
そのため、大学組織のことを広く深く理解できてこそ、初めて携われる仕事と言えます。
「人件費」を預かる人事部の仕事内容
「人件費」が組織の経営を圧迫しているのはどの組織でも同じです。
大概は人件費率を、いかに下げられるかが経営上の重要課題。
かといって、給与水準などを下げれば組織の士気が下がります。
特に大物研究者など、貴重な人材がライバル大学に流れ出てしまっては、大学としての品質が下がってしまいます。
逆に人件費の水準を上げることは簡単です。
ですが、少し上げただけでも、年間数億円単位の経費のカサ上げにつながったりします。
その上、一度上げてしまうと、元の水準に戻すことは一筋縄ではいきません。
そもそも、学生からの貴重な学費を人件費に注ぎ込むという発想自体が社会的バッシングの対象になります。
こういった大学経営上の重要課題をコントロールしているのも、人事部の業務のうちの一つです。
人事部は細かな仕事内容が多い
一般的な労務(給与計算や入退職手続き、社会保険の諸手続きなど)も、大学の場合は大変です。
理由は、非常勤講師や有期教授などが多いため、扱う人数が多くなるのが大学の傾向だからです。
特に理系が強い大学だと、国の補助金で研究員を採用することがほとんなので、労務で扱う人数がケタ違いに跳ね上がります。
例えば、中規模大学以上なら、総勢で数千人規模の教職員の処理を日常的に行う必要が出てきます。
教員採用について
ちなみに、教員の採用については、ほとんどの大学は人事部ではなく、「学部」が独自に採用を行っています。
つまり法学部なら法学部が、理学部なら理学部が単独で選考を行っているという形です。
教員採用は、研究者・教育者としての採用なので、その業績判断は同じ専門分野の教員しかできないからですね。
また、教員・研究者というのは、ある意味、その大学または学部の品質を示す商品ともいえます。
大学としてのステイタスを維持するためにも、教員採用は学部の聖域扱いのような位置付けです。
面接で、その大学での研究者について話題が出たときは、このあたりを認識しておきましょう。
教授の肩書きについて
よく「客員教授」や「研究特任教授」「招聘(しょうへい)教授」などと、ちょっとよくわかりにくい肩書きでテレビや著書などに出ている人がいますね。
まあ大学の教授なんだろうな、とあまり深く考えることもないと思います。
実は、これらは単に肩書きを貸してあげているだけの外部の人、といったニュアンスの人たちです。
1円も給料が出ていないケースがほとんど。
色んな意味でお互いにメリットがあるので成り立っている仕組みです。
大学にとっては広報価値がありますし、本人にとってはステイタスとして利用できたりするからです。
大学における人事戦略の一つと言えます。
とはいえ、内部関係者からすれば、この手の方々はほとんど無関係の一般人という感覚です。
面接で、テレビによく出ている大学教授の名前を出してコメントするときなどは、このあたりの状況を理解しておきましょう。
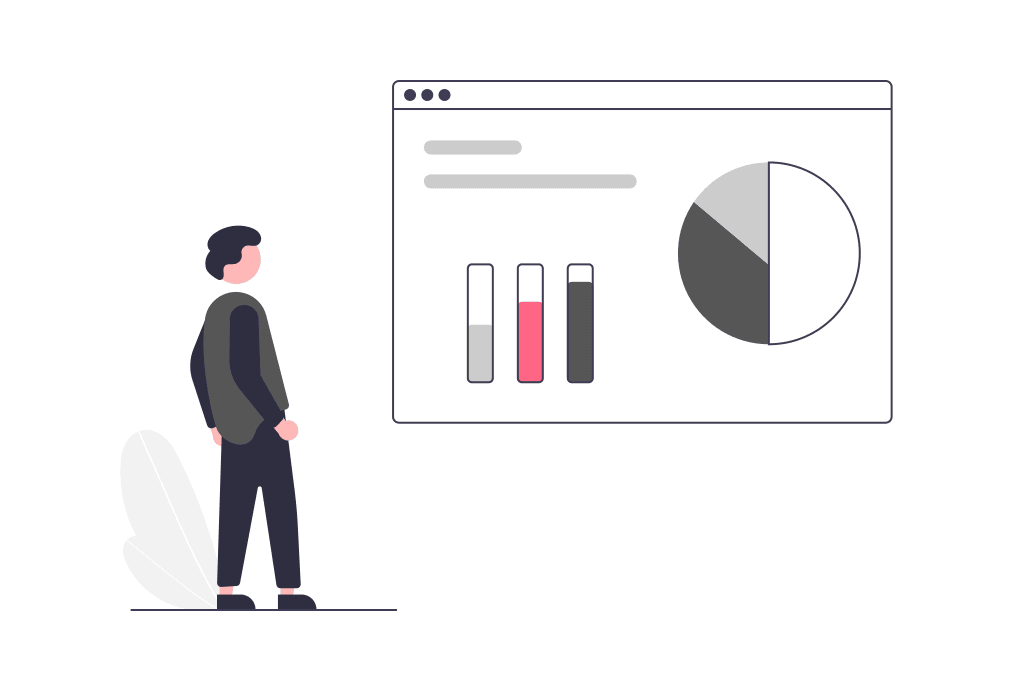
最後は経理の仕事内容です。
大学職員【経理】の仕事内容
経理という領域に今まで縁がなかった方は、経理なんて専門職は自分には関係ない、と思うかもしれません。
ですが、大学職員の場合は、人事異動で経理配属となるケースは普通にあります。
文学部出身だろうが外国語学部出身だろうが、辞令は組織側の論理で容赦なく発令されます。
経理の仕事内容に関心を持つことは重要
面接では、「経理部への配属もあり得ますよ」、と指摘することはよくあります。
この時、「想定外だった」という反応をしてまうとNGです。
逆に、経理経験はなくても、色んな仕事に興味関心を示してくれる応募者は、面接官の立場としては好印象を受けます。
大学の資産と通帳を管理する仕事内容
大学の経理といっても、企業と同じく基本的には、
- 送金・入金などの経理処理
- 資産管理や研究費の管理
- 予算編成・決算処理
などが中心になります。
そして、顧問監査法人の会計士や税理士と、会計的な課題と問題点を日々、議論します。
仮に下っ端で配属されたとしても、打ち合わせに同席したり書記をしたりで、いやでも財務知識が身に付きます。
さらに、日々の伝票処理で、1円の活動から100億円の活動まで、大学の「全ての」活動が「必ず」経理部の目を通ります。
それを通して、法人活動の舞台裏を正確に知ることができます。
そのため、経理経験は、真の大学の姿を理解できるといっても過言ではありません。
例えば、
- このままだと●年後には赤字になる、とか
- ●学部の存在が(財務的に)お荷物になっている、とか
- ●キャンパスは郊外にあるが、実は経営効果が高い
等々を、誰からも異論を出しえない「事実として」読み取れるようになります。
経理部長経験者が、後の事務総長などの大学管理部門のトップになることが多いのも何となく理解できますね。
採用面接でも、
- その大学の全体の収支規模はどれくらいなのか、
- そのうち学費収入の割合はどれくらいなのか、
- 補助金はどれくらいもらっているのか、
等々のキーワードを散りばめながら面接をすると、他の応募者と大きく差がつきますよ。
付属病院の財務的存在感をおさえておく
ちなみに、医学部を持つ大学の場合は、付属病院が生み出す収益へのインパクトが強烈です。
その点も豆知識的に仕入れておくと、視野の広さも示せて面接では有利。
例えば日本大学のように、大学全体の収入のうち半分以上は付属病院からの収入で占めている、といったケースもあります。
その他の参考記事
この記事が参考になった人なら、以下の記事もおすすめです。
「研究支援部」や「広報部」の仕事内を紹介する記事がこちらです。
大学ならではの「入試部」についてはこちら。
その他、以下のメニューで大学職員の情報を発信中です!転職活動に役立てて下さい!