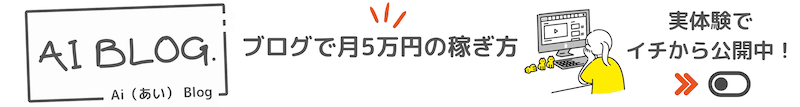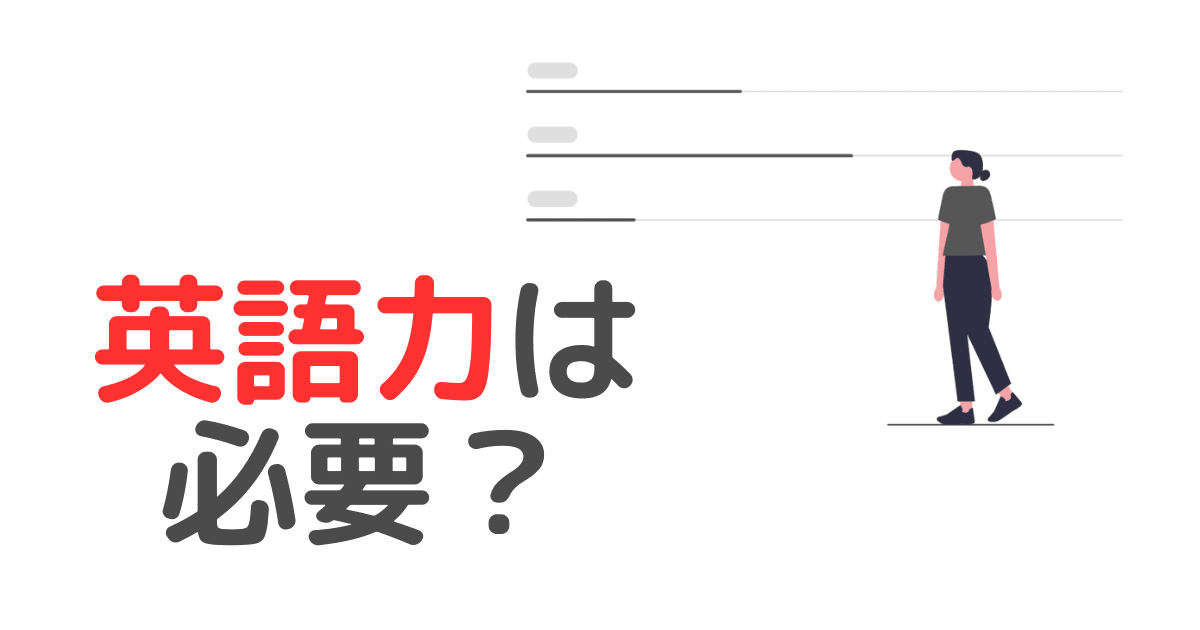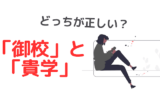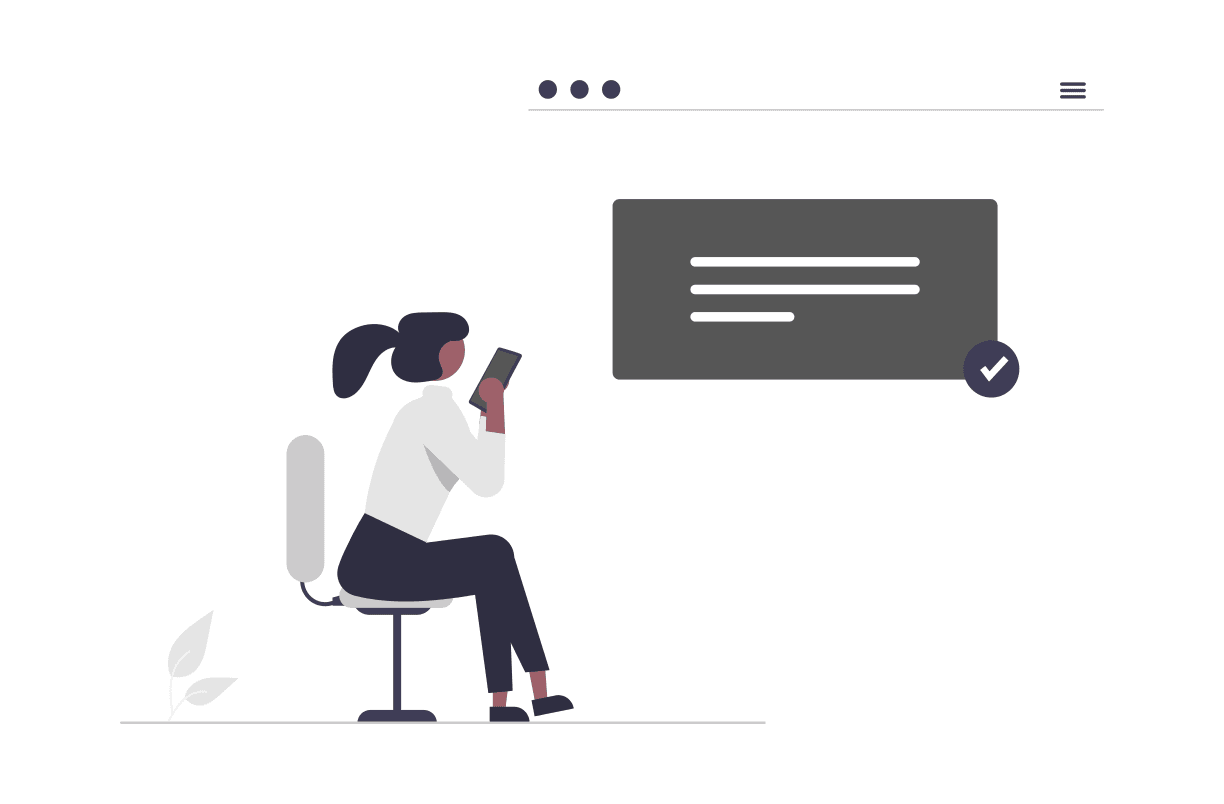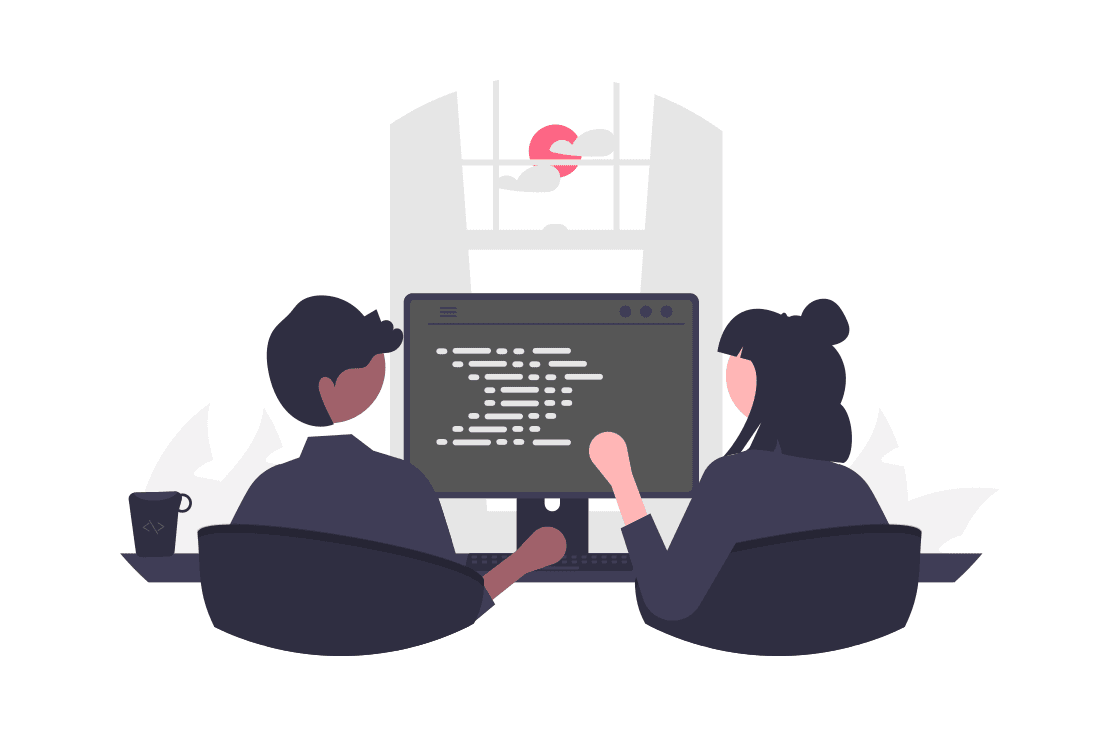TOEICスコアが600点台レベルで、語学力にコンプレックスを持っていませんか?
そのレベルだと、大学職員への転職は厳しいのでしょうか。
この記事では、そんな疑問にお答えできます。
最近、この大学職員カテゴリーへの訪問者数が急激に増えてきました。
内訳で見ると、なぜか海外からの訪問者数も3割以上。
そんなこともあり、外国の学位を取得されている方も視野に入れて、日本の大学職員と英語力の関係について語ってみます。
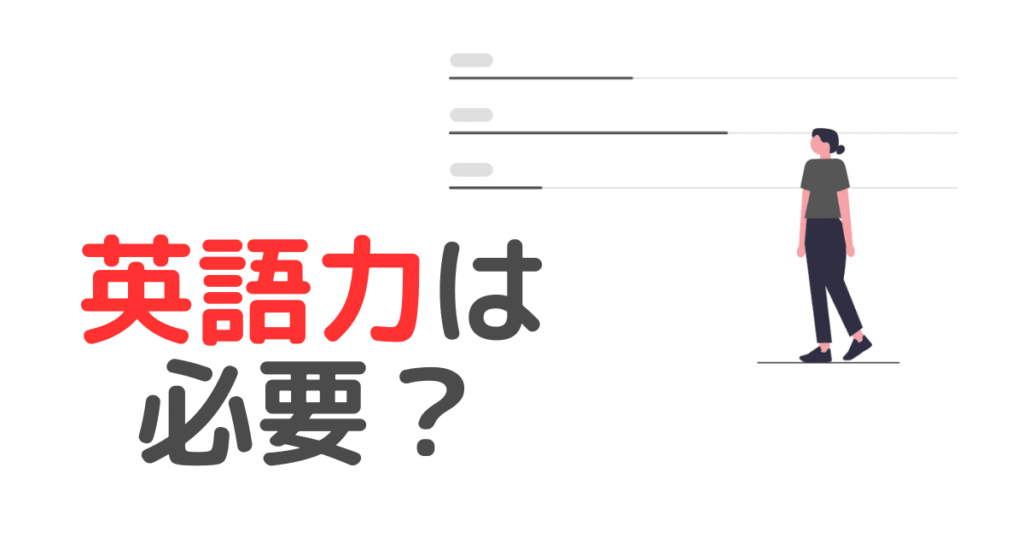
元大学職員のAI(あい)です!教務、国際、研究支援、経理、人事、学長室、と経験して20数年。早期退職を利用して引退。大学職員としての経験談をPR記事として公開中!
大学職員の採用面接と英語力の関係
まずは結論からです。
語学力があると有利
大学職員を目指す場合、
英語力があると問答無用で有利です。
その理由がこちらです。
- 今どきの採用トレンドとして、英語はできて当たり前という社会基準がある
- 英語力を磨いてこなかった応募者には、根拠なくネガティブな印象に繋がる
- 募集要領で「求める人材像」の項目等に、フレーズとして簡単で入れやすい
大学職員に限らず、英語力を評価ポイントにおくことはとてもわかりやすいです。
採用現場と英語力
分かりやすいがゆえに、職員採用チーム内でも、それに対して誰もNoと言わない空気感があります。
例えば、採用チームが次年度の職員採用方針を固めるミーティングなどの際も、かなり安易に、英語力を評価ポイントに挙げがちなのです。
今や英語はできて当たり前。
新卒の応募者でもTOEIC800点以上の学生が山ほどいる状況も、そういった空気感につながる理由です。
結果、採用時に英語力があると、問答無用で有利に働くのが現実です。
大学職員の仕事と英語力の関係
ところが、この記事の本題は、それと全く逆の方に向かいます。
入職後は語学力は不要
いざ入職したあと、その語学力がどれくらい仕事に役立つかというと、
ほぼ関係ありません。
学生部や就職支援センター、奨学金課や教務部、はたまた人事部や経理課、管財部や卒業生対応に至っても、ほぼ日本語オンリー。
日本の大学である以上、それでこの先も支障ありません。
大学のグローバル教育
とここで、近年のグローバル化について気になる人もいるかと思います。
確かに、グローバル化には、多くの大学で重点的に経営資源を投入しているのは事実です。
しかし、大学にグローバル化が求められているのは「教育面」について。
それは教育者の仕事です。
事務職員の領域ではありません。
職員が英語を使うシーン
とはいえ、確かに事務面でも英語との接点はあるにはあります。
が、それは、
たまに書類やメールを「読む」程度で、
外国人に対して「話す・書く・聞く」
といったシチュエーションは、まぁ無いです。
受験英語で十分
受験英語経験者なら、そのレベルで十分実務で活躍できます。
英語力が必要な実務とは
もちろん、英語力がないと仕事にならない事務部門もあります。
ですが、そこには、
- 英語圏で育ってきた日本人か、
- 日本の大学を卒業した外国人、
が何人かいて、彼・彼女たちに任せるのが通常です。
理由は、そこで求められる英語力は、
ネイティブレベル「だけ」だからです。
ネイティブの業務内容
ネイティブレベルの大学職員たちは、
- 大学間協定書の契約書作成業務
- 国際アライアンスへの加盟交渉
- 海外校開設への現地行政手続き
等々を、学長直結の部署などで行っています。
ネイティブでも苦戦している
実態としては、
ネイティブでさえも辞書や専門サイトを見ながら苦戦して業務をやっています。
高度な英語スキルがある場合
あるいはネイティブではなくても、海外の大学を卒業したくらいの高レベルの職員なら、
- 外国人教員の採用時に雇用条件などを英語で説明する
- 留学生向けに、英語だけで完結する授業環境を整える
- 海外からの訪問団の受入れ窓口として各種調整をする
といった業務を行っています。
英語力を駆使する部署は少数
これらは、大学全体の中で見ると、一部・少数といった位置付けです。
例えば、職員数が500人クラスの総合大学※なら、トータルで5名前後が一般的。
日本語だけで成り立つ
残り495人の職員の日常業務は、
日本語だけで成り立っています。
※「総合大学」とは、複数の学部を持つ比較的大きな大学のこと。対義語は「単科大学」や「複合大学」です。「複合大学」は分野特化型の大学で、例えば看護学部と薬学部がある医療系大学、といったイメージです。
大学職員と留学生の関係
あとは、国際センターといったような部署で、留学経験レベルの英語力は求められます。
ですが、そこではお世辞にも高度な英語力を駆使しているとは言えません。
主に中国や韓国からの留学生と日常的なコミュニケーションが取れれば充分、といった感じです。
大学での国際交流の仕事内容について興味のある方は、こちらが参考になります。
以上が、大学職員と英語力の関係についてでした。
続いては、転職活動の側面から具体的に見ていきます。
大学職員の採用面接でのポイント
ここからが重要ポイントです。
- 転職活動時には英語力が「必要」
- 実際の仕事では英語力は「不要」
という事情をよく理解して職員への転職活動に臨んでください。
内定者と英語力の状況
その上で、
実際の内定者には、英語力が普通レベルかそれ以下が大半である
という事実をおさえておきましょう。
英語力に関する具体例
まず、実際に面接官を担当するのは、現場の大学職員であることを理解しておきましょう。
実務の現場感覚では、英語の達人よりも、本質的な職員力がある職員の方が貴重な人材と映ります。
本質的な職員力というのは、主には、
堅実で、慎重で、きっちりとしたタイプです。
その切り口で見たときに、
「なぜTOEICの勉強を『堅実に』『きっちりと』やってこなかったのか」
といった趣旨で、語学力について質問するときはあります。
英語力不足について追求しているのではなくて、もっと別の本質的な意図をもった質問です。
そこの受け答えさえ的確にできれば、英語力がないからといって、それ自体が致命的な不合格ポイントになることはまずないです。
✔️面接時のポイント
例えば、
「社会的に英語が重要であることは承知していましたが、私の考えでは、その時間があればむしろ、今の仕事上のスキル向上に時間を充てていました。目の前の仕事を、人一倍充実させることの方が、職場に貢献できると考えていたからです。例えば今の仕事では、●●の知識が必要な部署ですので、その経験を積むために●●の習得に多くの時間を費やしていました。」
と、こんな感じの受け答えで十分です。
大学職員と英語力の関係
英語力がないと、まずは入口の段階で余計なネガティブ印象を持たれて不利に働きます。
英語力に自信がない場合
また、甲乙付け難い、何人かの応募者と横並びになった場合にも影響します。
この場合、最後は客観的指標の英語力の優劣で決定されてしまう、といった感じで不利に働くことがあります。
しかし、大学職員の中途採用プロセスでは、デメリットはそれくらいです。
つまり、
いくらでも他の要素で挽回できる、軽いデメリットです。
なので、致命傷として考える必要は一切ありません。
実際の内定者たちが、語学力堪能な人ばかりではないのがその根拠です。
英語力に自信がある場合
確かに、英語力が必要とされる部署への配属を前提にして、高度な英語力を条件とした求人をかける時があります。
要するに、専門職・技術職の採用ですね。
しかしそれでも人物面が優先的に見られます。
理由は、
その場合は、応募者全員がネイティブだから
です。
PRするべき点はやはり人間性。
海外の学位取得者、帰国子女、といった経歴があれば、それだけでスキルは伝わります。
その他のおすすめ記事
この記事が参考になった人なら、以下の記事もドンピシャなはず。
大学職員の採用事情を深掘りした記事がこちらです。採用経験者目線なので、参考になると思いますよ。
本気で大学職員を目指すなら基本知識は必須です。面接前にぜひ読んでおきたい、業界研究におすすめの書籍の紹介です。
大学職員の求人情報は?
「リクナビNext」で求人検索する時は「学校法人 大学 専任職員」で検索しましょう!
大学職員への転職に役立つ記事
その他、さまざまな切り口から情報を公開中です。
以下のジャンルから、転職活動に役立てて下さい!