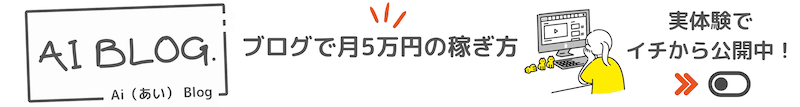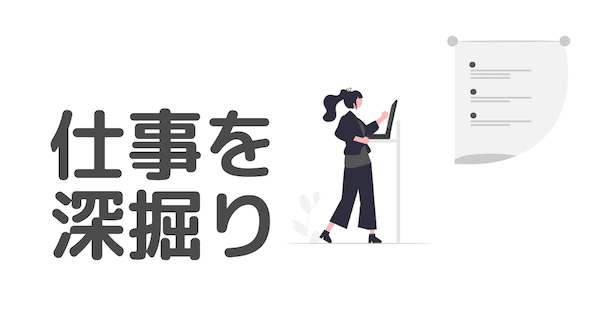転職活動で大学職員を検討中の方向けに、是非おさえておきたい仕事の中身を解説します。
ここで紹介する仕事内容をおさえると、大学事務のほぼ全てをカバー可能です。
かなり長い記事ですが、網羅することが目的なので、
保存版として、辞書替わりに使ってください。
それだけで、他の応募者たちを、大幅にリードできますよ!
元大学職員のAI(あい)です!教務、国際、研究支援、経理、人事、学長室、と経験して20数年。早期退職を利用して引退。大学職員としての経験談をPR記事として公開中!
大学職員の仕事内容【1】教学系
まず始めは、誰もがイメージできる学生部、教務部、国際部から紹介します。
これらの部署は、総称して「学生部門」とか「教学部門」と呼ばれたりします。
※ちなみに、その他の人事や総務、広報やIT関連などは「法人部門」とか「管理部門」と呼ばれます。それに加えて「研究支援部門」を理解できれば、大学事務組織の3つの柱を理解できます。
教学系の仕事内容【1】学生部
教学系の中から、まずは学生部の仕事内容から紹介します。
学生部の仕事内容
「学生センター」とか「学生課」などと呼ばれることが多い部署です。
具体例として、イメージしやすい学生のサークル活動を例に挙げてみましょう。
毎年、ある時期が来ると、大学が学生サークルを公認するための仕事が発生します。
各サークルが、公認サークルとして認めてもらうように大学に申請してくるわけですね。
職員は、申請のための応募要領を作成、それを学内の掲示板やホームページなどで広報します。
そしてその手続き内容や必要書類などをチェックします。
地味で単調な仕事です。
しかし、ことはそう単純ではありません。
その先が職員のメイン業務です。
職員は、このサークル申請を審査する学内の「会議」や「委員会」を手配します。
これは、大学の決め事は職員が決めるわけではないからです。
大学では、ほぼすべての決め事は、しかるべき会議体や委員会を通して決定します。
その事務的な舵取りをするのが職員の仕事領域。
厚さ10cmもある分厚い規定集を毎日のように読み込んだりしています。
決裁機関
そして、大学内での決め事をする会議体や委員会のことを「決裁機関」と呼んだりします。
その決裁機関の構成メンバーは、学内の全ての学部の教員から、バランスよく選出されて成り立っています。
職員の具体的な動き
職員の動きは次のようなイメージです。
職員は、決裁に至る学内規定などのルールを正確に把握して、
- スケジュールどおり、
- 不備なく適切に審議・決裁されるように、
- 関係他部署との事務調整で動き回る
といったことを意識しながら事務調整を進める役割を担っています。
✔️採用面接でのテクニック
このように、職員の役割は、大学内に定められている制度を、
- スケジュールどおり、
- 不備なく適切に審議・決裁されるように、
- 関係他部署との事務調整で動き回る
という点が主な役割です。
とすると、面接やエントリーシートで、
「学生生活がより良いものになるように、学生目線の様々な改善案を提案したいと思い大学職員を志望しました。」
といったようなコメントは、大学職員が裏方業務であることを認識できていない典型的な浅いコメントであることがわかります。
一方、
「組織の事務運営が不備なく実行されるように、私の長所である堅実な姿勢を活かして裏方業務で大学を支えたく思い、大学職員を志望しました。」
といった感じであれば、職員像を理解できている好印象なコメントになります。
続いては、教務部をみてみましょう。
教学系の仕事内容【2】教務部
教務部の仕事は次のような感じです。
教務部の仕事内容
- 授業の管理、
- 教室の管理、
- 履修の管理、
- 定期試験の管理、
- 成績の管理、
- 進級・卒業の管理
中規模以上の大学なら、経済学部の担当職員、とか、工学部の担当職員、といった感じで、学部ごとに専門の事務職員として配属されるケースが多いです。
これは、「学則」によってそれぞれの学部ルールが異なるからです。
大半はシステム作業
職員は、自分が担当する学部の学則を埋め込んだ学内のデータベースを駆使して日々業務を行います。
例えば、中規模以上の大学だと、一つの学部で3,000人ほどの学生が在籍します。
この学生「全員の」履修や成績などを、データを扱って、ミス無く統計的に操作して管理するわけです。
✔️採用面接でのテクニック
大学職員は、全般的に高度なシステム操作が必要です。採用時にもITスキルがあると結構歓迎されます。
具体例を見てみましょう。
学生データの操作は結構複雑
例えば、学生一人あたり、4年間で40コマも50コマも授業を受けています。
また、授業数が数千コマある大学も珍しくありません。
留学先での単位や、教職課程などの個別対応も複雑に絡んできます。
そういった中で、大規模データを一括して、
- 必修科目の充足状況や
- 選択科目の振り分け設定、
- 定期試験の成績判定、
- そして進級や卒業判定、
などを、システムやプログラミングを駆使して判定しているわけです。
教員との接点が多い
また、授業の担い手である教員との関係が密になります。
- 来年の授業名をどうするか、
- 何コマ担当するか、
- シラバスの作成依頼、
- 定期試験の問題作成依頼、
- その採点のやり取り、
等々、一つの学部に50人の教員がいれば、全員とこれら全ての調整を個別に行ったりしています。
✔️採用面接でのテクニック
大学教授は社会性に乏しく、基本的にわがままです。そんな中でも、うまく対人関係を築ける能力が職員に求められます。
具体的な事例
教務部の仕事について、ある例を挙げてみたいと思います。
ちょっと長いですが、知らない人には割と重要なポイント。
職員は学生の味方になって学生をサポートするといったイメージでは「ない」ことがよくわかると思います。
例えば、日本テレビのアナウンサーに就職が内定している、インスタのフォロワー数も10万人を超えている有名女子学生がいたとします(架空の設定です)。
その学生が、わずか1単位不足で卒業ができない状況に陥りました。
この場合、職員は、卒業要件に1単位足りていない以上、卒業させるわけにはいきません。
職員はあくまで事務の執行部門。
学則の枠組みの中で事務を動かすだけだからです。
しかし、そうすると学生本人もその保護者らも黙ってはいません。
たった1単位のために人生が大きく変わってしまう、と大きな声で窓口に怒鳴り込んできます。
その学生の家族には有力な政治家などにパイプがあったりして、その政治家が大学に圧力をかけてきたりします。
実家が資産家の場合などは、多額の金品を包み込んで、事務責任者や学部長宛に、卒業できるように直談判に来ることもあります。
それでも、事務側の答えはNoです。
理由は、「1単位足りないから」、それだけです。
何万人も卒業生がいる大学ですから、過去にも同じように学則を遵守して対応をしてきている以上、今回だけ特別に便宜を図った対応をするわけにはいかないのです。
仮に例外対応をしてしまうと、今度は、過去に同じような境遇で留年をした学生が、不公平な扱いを受けたとして、新たな問題も生じます。
このように、職員はあくまで決まり事をルール通りに、一切の解釈を入れることなく実行することがその使命です。
採用面接時の注意点
上の例でイメージできたかと思いますが、職員の採用面接などでは、
❌イノベーティブで柔軟な課題解決力があり、新しい提案を積極的に打ち出せる人材
というよりは、
⭕️保守的で前例踏襲型の堅実なタイプ
の方が大学職員に向いているという印象につながります。
✔️採用面接でのテクニック
とはいえ、募集要項には割と改革思考の人物像を求めているように書かれていることも多いと思います。
仮に応募要領にそのような謳い文句が並んでいたとしても、そこは冷静に見極めて対応しましょう。
冷静に見極めておくべき理由は、
「一次面接の面接官は現場職員であるケースがほとんど」
だからです。
採用HPの「求める人材像」などに記載されている美辞麗句は、人事部の採用チームが打ち合わせでパンフレット化させた謳い文句。
一方で、実際に面接をするのは現場の職員です。
現場担当者は、自分たちの現場目線で合否感覚を作ります。
そのため、大学職員の本来の姿、つまり保守的で堅実なタイプとして売り込む方が、一次面接レベルは通過しやすくなります。
続いて、国際関係の仕事内容です。
教学系の仕事内容【3】国際部
国際部の仕事内容について、次のような視点が気になるところですね。
- 語学力はどこまで必要?
- 海外出張はある?
- 周りの職員はどんなキャリア?
その他、
- 希望すれば配属される?
- 海外オフィスでの勤務の状況は?
このような視点で、国際部関係の仕事内容をこちらの記事で詳しくまとめています。
教学系の仕事内容【4】入試部
教学系の最後は入試部について。
入学試験は、一般の人でもイメージをしやすい仕事内容の一つかもしれません。
それだけに、面接でも他の応募者と差が出にくいネタです。
ですが、入試の仕事内容の「的確な理解」はとても重要です。
入試のように誰でも馴染みやすい話題を、あえて出すときの面接官の質問意図は、
「どれくらい大学職員のことを理解できているか」
をチェックする点にあります。
入試の仕事内容については、
- オーソドックな仕事紹介「以外の」内容で、
- 一歩踏み込んだ視点に着眼し、
- 面接に役立つ形で、
といったスタンスで、こちらの記事に詳しくまとめています。
以上が「教学系」と呼ばれる仕事内容でした。
ここからは「法人系」と呼ばれる業務領域の紹介に入ります。
大学職員の仕事内容【2】法人系
まずは、資産・財産を管理する部署から見ていきましょう。
法人系の仕事内容【1】資産・財産を管理する部署
管財部、と呼ばれるケースが多く、大学によっては施設部や管理部、法人部と呼ばれることも。
イメージが湧きにくいと思うので、少し紐解いてみます。
土地からPCまで管理
大学は、広大な敷地とともに複数キャンパスを所有し、
キャンパスの中には校舎・研究室などの建物を多く持ち、
校舎の中には膨大な数の椅子や机からPC・プロジェクター等があります。
大学は、これら全てを適切に管理する義務があります。
理由は、学生から預かった貴重な学費によって購入しているものだからです。
広大な敷地を管理
キャンパス、すなわち敷地は、大学経営の舞台そのものです。
管財部の仕事は、その所有者として、
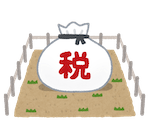
- 不動産管理
- 税金対策
- 近隣住民への安全対策
等々を行います。
また、
- 隣接地の買収計画
- 遊閑地を賃貸に出して収益事業化
- 新たなキャンパス計画(敷地取得計画)
等々も先頭に立って実行します。
結果、扱う規模が、数億・数十億円単位の仕事になります。
校舎・研究室などの建物を管理
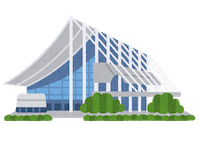
土地だけではなく、資産は全て管財部が管理します。
例えば、

- 校舎の建替・補修計画
- 食堂や自習エリア拡充など学生の居心地を改善
- 記念ホールやグランドなどの管理
なども管財部の守備範囲です。
PCやプロジェクターなどの備品まで管理
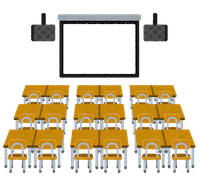
不動産だけではなく、動産も全て管財部の事務フィールドです。

- ホワイトボード、電動カーテン、モニターの買い替え計画
- エアコンや照明設備のリニューアル計画
- 自動ドアやエレベーターのメンテナンス等々
このような業務を、「償却資産を管理する」業務と表現します。
契約案件の管理

大学が主体となる契約関係も、管財部が対応します。
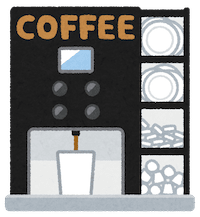
- 学内Wi-Fi等の整備のため通信事業者と契約
- 車、サーバーなど大型備品のリース契約
- 生協、ATM、コンビニ、自販機設置などの契約
いかに支出をおさえるか、日々コスト管理との戦いでもあります。
施設管理

ソフト面でも結構いろいろあります。
- 大臣などが学内講演する際などに、SPを配置するなど警察と連携して安全対策
- 清掃業者と調整して、早朝・深夜に学内衛生管理
- 天災、震災、学内事故・事件などの危機管理対応

防犯カメラのモニタリングなどもやっています。
といった感じで、管財部は大学の資産・財産を網羅して把握し、それらを職員が管理・運営しています。
支出の管理
管財部のもう一つのポイントは、これら「全てを正確に隅々まで把握」する必要があるという点です。
理由は、全てにおいてお金の支出を伴う動きになるからです。
学費収入という予算上限を超えない範囲で管理をする必要があるからですね。
絶妙なラインを落とし所にして、かつ効果を最大化することが求められる仕事です。
✔️採用面接でのテクニック
管財部は、大学事務部門の中でも主流の部署です。
採用面接などでは、きっちりとした性格で、マメな上にやりくり上手な支出管理ができる性格をアピールすると、面接官には好印象を与えられます。
法人系の仕事内容【2】寄附金を扱う仕事
続いて寄附金を扱う部署の紹介。
大学ならではの部署です。
寄付金管理は重要戦略
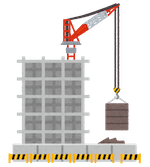
卒業生などからの寄附金を大学の貴重な財源とし、そこを重要戦略としている大学は多いです。
寄付金を財源として校舎を建て替えたり、寄付者の名前をつけた記念ホールという名目で名物校舎を作るなど。
寄付が多いと大学の価値も上げやすいです。
職員の仕事内容
その寄付は、高額寄付者だけで成り立っているわけではありません。
1人1,000円でも寄付は成り立ちます。
そのため、例えば10億円を目標とした募金キャンペーンを実施した場合は、寄付の受付数は数万件以上にのぼります。
これら全ての寄付者に誠意を尽くして職員が対応し、丁寧に細かく寄付手続きの説明をするのが職員の仕事になります。
仕事で苦労する点

寄付の手続き自体は、書類をかわす程度なのでそれほど複雑ではありません。

ですが、ある寄付者が今回は1万円の寄付だったとしても、以前に1,000万円の寄付実績がある、といったこともあり得ます。
ですので、実際に対応をする職員は、全ての寄付者に対して礼を尽くした対応が求められるので結構神経を使います。
ご年配の方などは、札束を抱えてアポなしでフラッと寄付金課に立ち寄ってきたりしますので、それが何百万円にものぼる場合は、札束を数えるだけで神経が疲弊してしまいます。
寄付の御礼を形にする業務

また、大学としての誠意のあらわれとして、
- 大学グッズや機関誌を贈る
- 寄付者銘板(校舎に氏名を刻み込むみたいな)を作成する
- 御礼の会合(寄付者を一斉に招待して学長と一緒に立食パーティみたいな)などを開催する
などのパフォーマンスを行うことも必要になってきます。
もちろん、対象者数は数万人にのぼります。
✔️なぜ高額寄付をするのか?
社会には、数億円規模で惜しみなく寄付する方が結構存在します。
その理由は簡単で、寄付をした方がその人にとって有利だからです。

例えば、起業して成功し、10億円の利益が出て、それに対して20%の2億円の法人税がかかることになったとします。
しかし、その利益の10億円を使って慈善団体や非営利法人を立ち上げれば会社の利益は無くなるので、2億円の法人税がゼロになります。

そして、その利益で立ち上げたその非営利法人には、自分が理事長になります。
そうすると、非営利法人として1億円くらい大学に寄付しておいて、残額は非営利団体の理事長としての給与等にして、法人税を払うことなく自分の給与収入に充てられます。
節税対策を通して高額寄付を促進するような社会構造になっているため、大学も寄付には重点的に力を入れるわけですね。
基金を管理する
さて、上の例で挙げたように、寄付金を建物などに使うことを、寄附金を「資金」として活用する、といった言い方をします。
もらった20億円の寄付金を、そのまま20億円の校舎建築費用として使うパターンですね
ここで、大学を知るにあたっては、同じ寄付でも「基金」という仕組みがあることを理解しておく必要があります。
基金とは

基金とは、得られた寄附金を使わずに貯金するようなものです。
そしてその貯金を運用することで、大学の研究・教育活動に充てていくやり方です。

例えば、寄附金として得た100億円を「基金」として運用し、その運用実績、例えば年率3%であれば3億円を、学生の奨学金などに還元していくやり方です。
この基金戦略は、昨今の大学にとっては重要戦略の一つとなっています。
早い段階から基金の拡充に着手してきた大学などは、今や100億円から600億円規模の運用基金を持っているところもあります。
採用面接の際も、こういったキーワードを散りばめて志望動機などをコメントすると、まさに経験者採用の応募者らしく、社会がよく見えている応募者として好印象につながりますよ。
ちなみに米国バーバードやイェールなどは、2兆円から4兆円規模の基金を作り上げています(もちろん世界最大規模の基金です)。
✔️採用面接でのテクニック
大学職員は、事務の仕事といっても対人業務がそれなりにあります。
しかもその対象は、学費を払ってもらっている学生や保護者だけではありません。
寄付をしてくれる卒業生などは、会社経営者など社会的地位が高い方も多いです。
当然、対人業務にあたる職員の対応が、その大学の印象に直結します。
ですので、採用面接でも、良い印象を与えれるマナーの理解は、評価ポイントに直結します。
例えば、
- 送付状の正しい書き方
- 面接時の入退室の仕方、座り方
- 大人感のあるフレーズの使い回し
- 上座と下座の違い
- 挨拶をするタイミング
こういったことは必須条件です。
以前、TOEICスコア満点で、ハイキャリアの応募者が、カカトを引きずって歩くタイプだったので、それがネガティブ印象に働いて最終面接(役員面接)で不合格となった実例もあります。
応募にあたって、大人ウケ対策は必要不可欠です。
マナー対策に自信がない方は、基礎から体系的に学びましょう。
そのあたりの信用度が高いのは、問答無用で「リクナビNEXT」。
採用担当者自身が、このコンテンツで学習しています。
法人系の仕事内容【3】総務・人事・経理の仕事
続いて、総務・人事・経理に関する仕事内容。
この部門の仕事内容を理解することは、かなり重要ポイント。
もちろん、企業にも同じ部署はありますね。
あえて仕事研究などしなくてもいいのでは?と思われるかもしれません。
ですが、同じような部署だからこそ、大学ならではのエッセンスを抽出可能です。
そうすると、企業と公的機関の線引きが際立ち、大学のことがより深くわかるようになります。
ここは重要なので、別の記事で詳しくまとめています。
法人系の仕事内容【4】広報の仕事
続いて広報部の仕事です。
まずは、大学のホームページ。
これを運営しているのは広報部であることが一般的です。
職員組織の立ち位置
事務組織である広報部は、その運営方針を決定しているわけではありません。
職員は、運営方針の「案」をたくさん立案する役割だけを担っています。
- ホームページのリニューアル案、
- SNS新規立ち上げ案、
- それらの目的や背景、
- 予算の見積もり、
- 導入効果、
等々を、客観的な根拠を示しながら資料として形作るだけです。
経営方針の決定機関
そして、その案は、主に教員で構成される広報関係の戦略会議で審議されます。
その会議体での審議結果を受けて、はじめて職員は、決定事項通りにWEB制作業者などに発注して作業を進めていくことになります。
決定権のある審議体は教員で構成されている
ちなみに、このような会議体の構成員は、ほぼ100%教員で構成されています。
それらの教員は、全学部から数人ずつ、バランスよく選出された教員たちです。
会議の実態
ところが、構成員である教員は、上司である学部長からその委員をやってくれと頼まれたから仕方なくやっている、といった感じが一般的です。
そもそも教員というのは、自分の研究業績を上げることが本来の仕事。
研究業績こそが研究者としての生命線なので、研究活動だけにエネルギーを注ぎ込みたいのが本来的な教員のスタンスです。
そのため、大学の行政活動などには関心が薄いのが通常です。
ですので一般的な教員感覚は、「手当も無いし、時間が取られるだけだけど、お役目だから仕方がない」、といった感じで会議に出席しています。
結果、提案されている大学の経営方針に特に議論することもなく、早めに会議を終わらせたいと思ってただ出席しているだけ、というのが実態です。
職員のやりがい
そういった実情から、広報戦略を審議決定する会議体がある、といってもそれは単なる形だけのもの。
なので、実際は職員がうまいことコントロールして事務側が思い描く方針で広報戦略を運営できたりします。
まさに官僚のようなイメージですね。
広報を例に挙げましたが、このような構造は、ある程度他の部門にも当てはまると言っていいかもしれません。
それが大学運営の実態だということを理解しておけば大丈夫でしょう。
このような職員像を冷静に見極めた上で応募してくる方のコメントは、面接官にかなりの好印象を与えられます。
✔️採用面接でのテクニック
面接で「職員になってやりたいことは?」などと聞かれた時に、的外れな夢物語を語ると一発退場です。
的外れな夢物語とは、大体次のようなパターン。
- 学生の役に立つ職員になりたい
- 大学の国際貢献に役立ちたい
- 就職部で学生相談業務で役立ちたい
このあたりのコメントは、聞かれない限り自分からコメントするのは避けた方が無難です。
ポイントは、ここまで見てきているような職員の立ち位置を理解した上で、あくまで裏方業務であることを踏まえておくこと。
その観点をうまくコメント上に散りばめられれば、非常に現実的で的確な発言として受け止められます。
その他の広報部の仕事内容

例えば、学内の研究者が、学術的な表彰を受けたとします。
そういった場合、広報部がそのトピックをいち早くキャチしてプレスリリース、大学のブランド価値を高めていくことも重要な業務です。
そのため、学内の全ての教員たちの研究活動に普段から敏感にアンテナを張り巡らせておく必要があります。
メディアの世界は、1日でも情報が古くなると広報価値が下がってしまうからですね。
研究面だけではなく、教育面にも目を光らせておく必要があります。
例えば、海外の有力大学と新たな単位互換制度が始まったとします。
となると、その制度や相手大学の詳細を把握してプレスリリースし、国際色豊かな大学として世間にアピールするわけです。

また、学生の体育団体が全国大会の決勝戦やオリンピック最終選考のレースに出るようなときは、当日の試合会場に足を運んで取材・撮影などを行います。
休日勤務が発生することになりますが、球場やスタジアムでの仕事はそれなりに気分が高揚するので、やりがいも感じられるかもしれません。

さらに、マスコミ各社との付き合いも重要です。
多方面に渡って取材申請が入ってくるため、その取材価値を見極めて判断をする必要があります。
事前に聞いていた取材趣旨を間に受けて対応したものの、いざリリースされた記事内容はとんでもない批判記事だった、というのはよくある失敗談です。
取材を受けた大学関係者のコメントが、マスコミ側の都合のいいように使われていただけ、といったことが山ほどあるからです。
日常的に記者やライターとコミュニケーションを取り、様々な情報交換を繰り返してその辺りの駆け引きの温度感を養っていくことが求められます。
続いて「研究支援系」の仕事内容の説明に入ります。
大学職員の仕事内容【3】研究支援系
研究支援とは、教授の研究をサポートする部門の仕事です。
教授の研究をサポートする部門
研究支援部などといった呼び方をされていて、これもまたどこの大学にも必ずある部門です。
補助金の管理
研究をサポートすると聞くと、アカデミックな印象を受けるかもしれません。
しかし実際は、補助金の申請業務と、その補助金の管理業務がメインです。
職員の仕事を見る前に、まずは、研究者の動きを理解すると、よく理解できると思います。
研究活動とは?
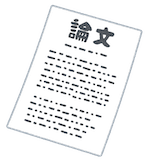
教員が研究を進めるにあたっては、研究費が必要不可欠です。
研究とはすなわち論文発表、これがその最終目的になります。

論文発表こそが研究者の生命線で、その論文作成のために、
- 書物が必要
- PC、PCソフト、プリンターその他周辺機器が必要
- 学会登録費が必要
- 国内外への出張が必要
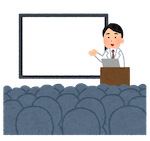
と、様々な経費がかかります。
この経費を国が補助するという仕組みで、日本の学術文化の発展は成り立っています。
職員の仕事内容
ここで職員の出番となります。

研究費補助金は税金で成り立っていることがほとんどなので、その申請手続きは冗談抜きで細かく、煩雑で、膨大です。
その補助金の申請手続きだけで、本来の研究時間が大幅に裂かれると言っていいほど大変です。
これを、職員が事務面でサポートしているわけです。
不正管理
また、研究費の使用は、公私の区別がつきにくいことも多くあります。
研究活動という名目で、書籍やPCや出張を不正利用するケースが後をたちません。
これを防ぐために、補助金ごとに、物凄い量のルールが定められています。
職員は、そのルールを、補助金内容ごとに全て正確に把握します。
不正と疑われそうな使い方とならないように管理し、年度末には、適正な補助金使用実績報告書を、大学の名誉を背負って作成します。
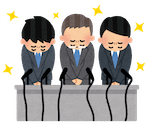
ここで「不正」と指摘されるとマスコミの格好のネタ。
報道に至ると大学の名誉はガタ落ちします。
仕事で苦労する点
研究活動で発生した領収書や請求書や参加証明書など、全てをルールどおり的確に管理する仕事が職員のメイン業務。
ルールがあまりに細かい上、一見、不条理なルールも多いです。
そのため、教員の理解が得られず、その点で職員が苦労する場面が多いことも特徴。

「そんな証明書、あるわけないじゃないか!!常識的に考えろ!!」
と、研究者の怒りの矛先が職員に向けられるケースがあったります。
理系の研究費管理
さらに、大学での研究と言うと、メインは自然科学系になります。
いわゆる理系の領域ですね。

工学や薬学、エネルギーや建築などの研究機器や研究設備は、どうしても高額になりがちです。
例えば、ニュートリノ研究では、研究施設構築費だけで100億円以上、年間維持費だけで20億円以上、といったイメージです。
とりわけ医学部がある大学は、それだけで他の大学よりも研究費がさらにケタ2つほど異なってきます。
逆に、人文・社会科学系は金額的には微々たるものです。
経理業務に近い仕事内容
このように、研究支援部は研究費を管理することがメイン業務なので、実際はお金の支出管理を適切に行う経理業務に近いという言い方ができます。
✔️採用面接でのテクニック
理系の学部が強い大学や、医学部、薬学部があるような大学では、この研究支援部の存在感は大きいです。
膨大な額にのぼる研究資金を、国によって定められたルールを漏らさずに理解した上で管理する必要があるからです。
採用面接では、例えば、自分が家電製品やスマホなどを買った時、製品仕様書や取扱説明書などをきっちりと読み込んでから扱う、といったタイプであることをアピールできれば、適性としては好印象につながるでしょう。
逆に、とにかく電源を先に入れ、直感で設定を進めて、何となく表面上うまく作動させる、といったタイプでは務まらない業務です。
次で最後!
大学職員の仕事内容【4】その他の主な部署
外部者にとってはなかなか知る機会がない、その他の大学職員の主な部署を紹介します。
大学職員を目指している方なら把握しておきたいところは次のような部署になります。
- システム関連
- 図書館
- 付属小・中・高等学校
- 卒業生関連
いずれも詳細まで理解することは不要です。
このような部門がメインとして位置付けられているんだ、くらいの理解で大丈夫。
システム部・図書館
システム部や図書館などは、実は学内予算規模がケタ違いに高いトップ2の部署と言えます。
言われてみればそうかもしれないけど、皆さんにとっては意外と盲点ではないでしょうか。
両部署の所属職員数も圧倒的に多数なのが通常です。
つまり、学内でも影響力が大きな部署と言えます。
こんなところが見えていると、いかにも社会人経験者らしくて、面接では好印象を与えられますよ。
とはいえ、システム部も図書館も、職員採用のルートとしては、7〜8割程度を専門職採用の形態で採用している大学が多いです。
いずれも、修士・博士号の上位学位を持っている職員が多いことも特徴のひとつ。
逆に、一般職員であっても、システム部や図書館に配属となる可能性はあります。
つまり幅広い視野が必要なジェネラリスト職員は、こういったスキル重視の部署の経験も積んでいくことが必要だからです。
付属小・中・高等学校
大学職員とはいえ、雇用主は学校法人です。
そのため、組織上同じ学校法人であれば、付属の小中高等学校に人事異動で配属されることは普通にあります。
そして大学は、監督省庁である文部科学省、つまり国のルールを遵守して運営されていますが、
小中高等学校の場合は、管轄が東京都や大阪府などの地方自治体に変わります。
従って、ベースとなるルールが違ってくるといったことを知識としておさえておきましょう。
ちなみに、付属校、ではなく、「系列校」や「提携校」、となっている場合は別法人であることの方が多いです。
この場合、系列校や提携校は別法人なので、職員の人事異動の対象ではありません。
卒業生関連
卒業生に関連した事務を扱う部署は、大学ならではの部門ですね。
やっている仕事内容は、
- 卒業生の名簿管理
- 卒業生向けの機関誌発刊
- 大学主催の同窓会開催
といったことが主な業務内容です。
大学は卒業生あっての組織でもあるので、学内での位置付けも重要度は高い方。
関連して、寄附金が集まりやすいのも特徴。
例えば、新しい校舎を建てるという名目で、3年をかけて10億円の募金活動を卒業生に対して行う、といった一大キャンペーンが実施されたりします。
そのような時に、職員はその目的達成のための実働部隊として活躍することになります。
その大学の卒業生が社長を務めている企業などに出向いて、母校への寄付のお願いをして回るといったこともやります。
意外かもしれませんが、こういった仕事になると寄附金ノルマ達成率などの成績ベースで執務評価が行われたりもします。
「大学職員の仕事内容」のまとめ
以上、大学職員を目指すなら、仕事の内容については大体この記事の内容をおさえておけばまず大丈夫。
あとは、
- 教育機関としての大学
- 学校法人としての大学
と高等教育機関としての視点で理解しておけばほぼ完璧です。
その点がおさえられるような、有益な書籍一覧を別の記事にまとめています。
あまり負担にならないように、5冊に絞って紹介しています。
かなり参考になると思いますよ!