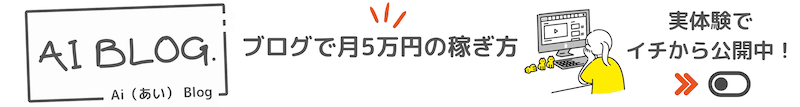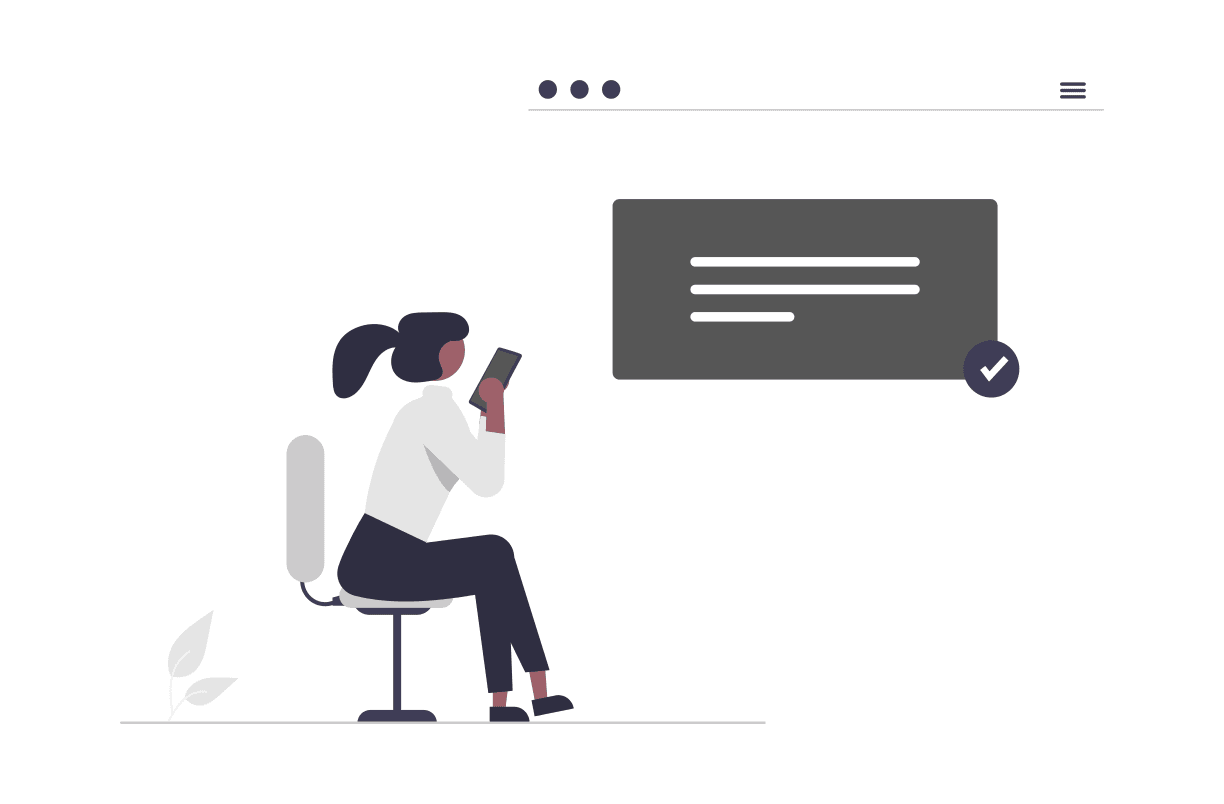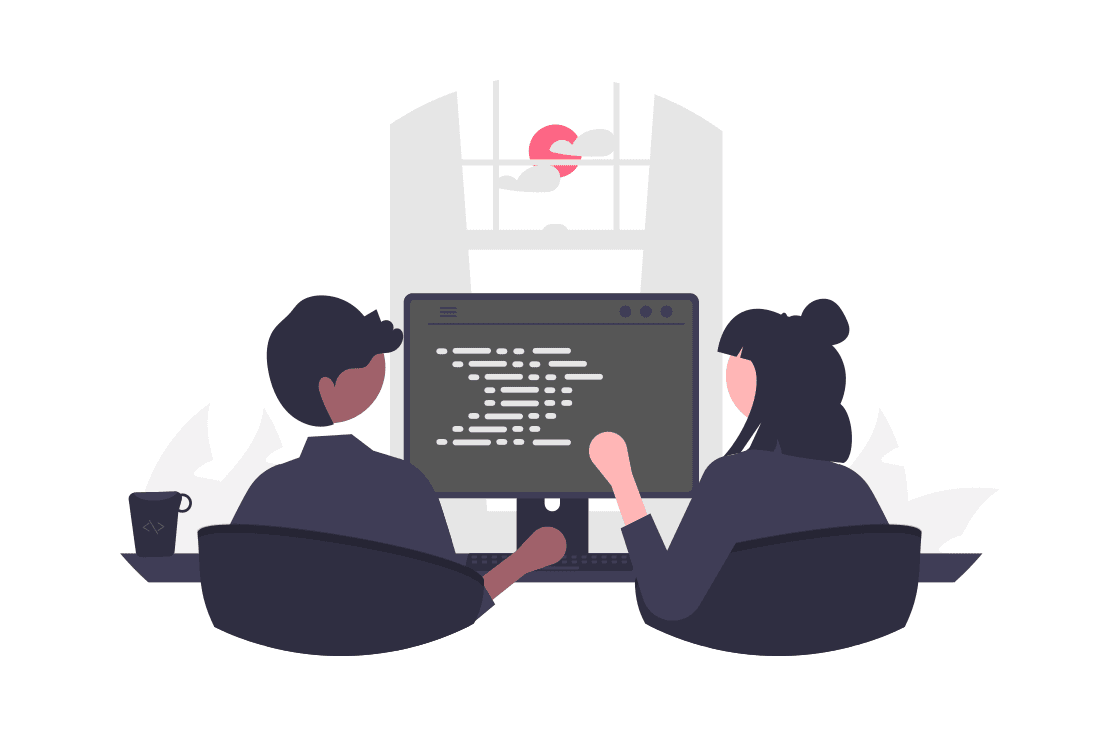ホワイト転職の代表格として、完全に定着した私立大学職員。
とはいえ、転職は絶対に失敗したくないですね。
気になる待遇は、今の職場と比べてどうなるのでしょうか。
大学職員の具体的な年収事情を公開します。
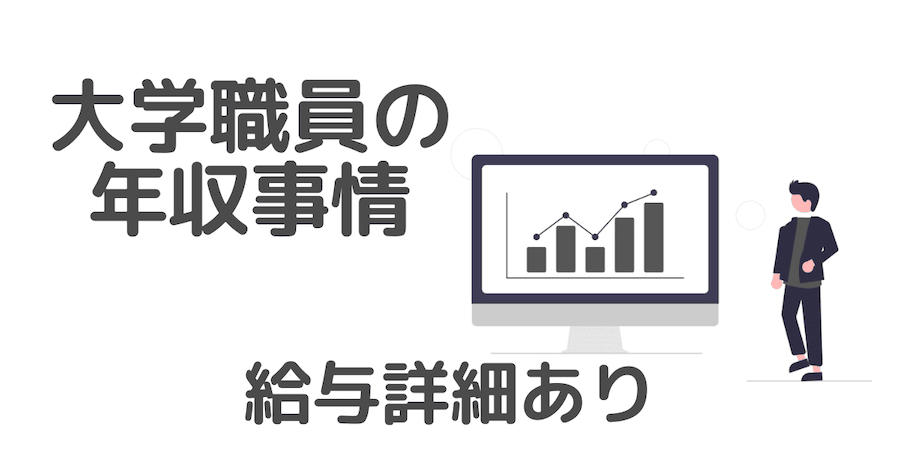
元大学職員のAI(あい)です!教務、国際、研究支援、経理、人事、学長室、と経験して20数年。早期退職を利用して引退。大学職員としての経験談をPR記事として公開中!
後半では、隠されているカラクリも公開しますね!
私立大学職員の待遇(給与詳細あり)
日本人の平均年収は467万円(国税庁の統計、平均年齢43歳)。
民間のdodaの調査でも、40代で日本人全体の平均年収は500万円前後とのことです。
年収は高水準
この統計を見ると、私立大学職員の給与がそれなりに高い水準にあることがわかります。
大学職員なら30代で年収900万円までいきます。
年収900万円なら、手取りは720万円程度。
30代で毎月60万円の可処分所得です。
男女の差が全くないため、職場結婚組の場合なら、世帯収入はほぼ倍増。
職場結婚組の可処分所得は、毎月120万円近くになります。
業務環境が穏やか

さらに、大学職員は比較的仕事が楽です。
残業は少なく、夏休みも冬休みも多く、有給休暇も取得しやすい労働環境。
大手エリート企業でズタズタになるまで働き尽くしながらの高給取りもいいですが、大学職員なら安定と余裕が約束されます。

穏やかで充実した人生が送れます。
ちなみにこの記事で紹介する年収事情は、中堅以上の私立大学に焦点を当てています。

それらの年収状況がわかる理由は、大学の人事部間には、私立総合大学の人件費を経営課題とする「正規の研究会」があるからです。
その研究会を通して、大学全体の詳細な待遇状況がデータや資料として出回っています。
初年度は年収600万円前後(諸手当込)
では、具体論に入っていきましょう。
初任給は標準的
大学職員の場合、新卒の初任給は20万円強です。
割と標準的です。
2年目で年収400万円前後
新卒2年目になると、賞与(ボーナス)がフルで支給されて、年に3回、合計6.9ヶ月分。
といった感じです。
これで、新卒2年目で400万円前後の年収です。
3年目以降も機械的に昇給
給料は、年齢や職歴に応じた給与テーブルの基礎表に沿って、毎年、自動的に昇給します。
有給休暇を100%消化しても、執務態度が異常に悪くても、能力評価の良し悪しは全く関係なし。
全員が漏れなく毎年昇給します。
昇給しないパターンは、例えば、無断欠勤1ヶ月とか、身勝手な休職など、あり得ないほど極端な場合くらいです。
給与テーブルの仕組み
転職者の場合、入社時の年齢が29歳なら、29歳の給与テーブルに機械的に当てはめられます。
29歳くらいなら、月額給与30万円弱、ボーナス6.9ヶ月分プラス残業代で、年収は600万円近くになります。
残業代はフルで支給
労働基準法をきっちりと遵守するのが大学組織。
残業も、超過時間全てが手当の対象になります。
この年代だと残業代の1時間単価は3,500円くらい。
30歳半ばで年収700〜900万円(諸手当込)
そして30歳を過ぎたあたりの年代は、次のような感じです。
役職手当がつく
この頃には、大半の人に役職が付き始めます。
「主査」や「主任」への昇格といった感じです。
給与テーブルが上がる
すると、給与テーブルが別の給与テーブルに代わり、一気にベースが跳ね上がります。
そして、次のような状況になります。
結果として、この年代の平均的な年収は800万円程度。
忙しい部署なら、月40時間程度の残業が発生し、その場合は残業代だけで年間プラス100万円程度になります。
女性職員の例
この年代で昇格が遅れるパターンは、育児休職などで数年のブランクがある女性の場合がほとんどです。
例えば、二児を出産して、育児休職を連続して取得すれば、4〜5年の空白期間ができるからですね。
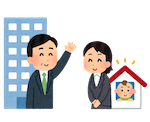
その場合は、復職後、各種手当は最低限。
また、短時間勤務(9:30〜16:30など)の制度なども利用するパターンがほとんどです。
この場合、年収はその年代での最低ラインとなります。
それで大体700万円いくかいかないかくらいです。
続いては、大学職員の将来像を見ていきましょう。
40歳前半で管理職、年収1,000万円超
40代前半で、一部の職員は課長などの管理職になり始めます。
管理職になれば、給与テーブルも手当も数段上がります。
課長手当だけでも月額10万円超。
もちろん賞与込みで、年間18.9ヶ月分の支給に反映されます。
ただし、管理職に残業代は支給されません。
そんな感じで、管理職1年目の額面は、
月額60万円ほど、ボーナス400万円ほどで、年収1,100万円程度です。
40歳を超えた職員の特徴
このあたりの年代になると、あからさまに仕事をしない職員がたくさん出てきます。
幸か不幸か、何も努力しなくても、完全に年功序列でここまで昇給してくるからです。

頑張らなくても、昇格は無くても、この先も機械的に給与テーブルが上がるため、昇給はしていきます。
給与が下がることはない
その上、給与水準が下がることはあり得ません。
なので仕事に対して上昇志向や責任意識が薄れてくるのは、人間心理として自然なことかもしれません。
そして、残りの普通な社会人感覚を持つ(まともな?)職員が、管理職に昇格するといった感じです。
40代後半以降の状況
その先の職員キャリアは千差万別です。
基本給テーブルは上がり続ける
最低ランクの管理職クラスのままキャリアを終えたとしても、基本給テーブル(年齢や職歴給)は自動的に上がり続けます。
それで、最終的な年収は、最低でも1,300万円超といったところです。
残り定年まで20年、として計算してみましょう。
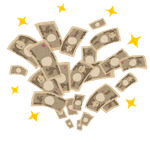
この先、2億6千万円の給与収入が約束されている、と言い換えられます(実際は、さらに退職金や企業年金も付加されます)。
部長クラスの状況
一方、50歳前後で部長クラスになると、ベース給与はもちろん上がります。

さらに、毎月の「手当だけで」プラス30万円前後。
年収ベースで2,000万円に近づくレベルになります。
最も高いレベルの状況
最高ランクは事務総長や理事などというポジションです。
こうなると「手当だけで」毎月プラス90万円前後。
さらに、社用車や秘書が付き、飲食などの接待費も支給されたりします。
PCやスマホ、通信代やなども経費で落とすことができるので、出ていくお金も激減します。
ヒラ社員や係長どまりのケース
逆に、本当に上昇志向がない職員が全体の半分近くいるのが大学組織。
実際の実務は、派遣職員やアルバイトさんに処理させて、正規職員は終業時間ちょうどにさっさと先に帰ってしまっているケースなどは珍しくありません。
この手の職員でも、ただいるだけで、年齢を重ねていくうちに給与テーブルの上限まで達するので、年収は1,000万円近くに達します。
退職金は3,000万円〜4,000万円前後(役職による)
退職金は、退職直近の役職や基本給がベースとなって算出されます。
転職者の場合は年齢給の部分だけが出遅れるため(勤続年数に比例する給与部分)、ややその点が不利。
その上で、転職者が中位レベルの役職(課長クラス)で定年退職した場合なら、退職金は大体3,500万円くらい。

部長クラスなら「軽く4,000万円」は超えてきます。
共働きのケース
かつて、高卒で入社、47年間勤務し、最後は主査、といった男女夫婦職員のケースで、勤続年数の計算式が有利に働いて、二人で9,000万円近くの退職金、という事例もありました。
1年でも早く入職できると、生涯賃金がグッと変わってきます。
定年は65歳
民間企業の場合は定年が60歳のところも多いですが、大学は定年が65歳のケースが多いです。
理由は、大学内の給与設計は、教員・研究者を対象として作られているからです。
大学教授と大学職員は同じ舞台
研究活動というのは、一般的なサラリーマンと違って、生涯現役に近い形で知的な労働対価を生み出せます。
この背景で、教員と同じ給与設計に乗っかってきた職員も、定年年齢が65歳のところが多いわけです。
生涯賃金でシミュレーション
60歳を超えても、好条件のまま5年間多く働けるということは、すなわち年収×5年分の収入が余分に得られることを意味します。
ヒラ職員でも、5年で総額5,000万円〜6,000万円が生涯賃金に上乗せされてくる計算です。
目先の待遇だけでなく定年年齢も加味して転職先の大学を検討することをおすすめします。
企業年金あり(年間200万円前後)
老後のことが気になる方は、大学の場合、独自年金を制度化しているところが多いのでおすすめです。
いわゆる確定給付型です。
一定の条件(勤続20年以上など)を満たせば、あとは退職直近の役職や基本給与に応じた年金が、「別枠で」支給されます。

もちろん、退職してから亡くなるまでずっと勤務先から支給。
- 国民年金、
- 厚生年金・私学年金に加えて、
- 企業年金、
までもが受けられる、至れり尽くせりの人生設計です。
年金の相場
金額的には、中位レベルの管理職で退職した場合で年間200万円前後(の別枠支給)が多いです。
仮に85歳まで受給したとすれば、200万円×20年で4,000万円が、一般の人たちよりも生涯賃金に上乗せ支給される仕組みです。
情報の入手方法
就活や転職先を考えるにあたって、
- 余暇
- 安定
- 軽ストレス
- 高待遇
などを重視する方には、私立大学の事務職は最有力の選択肢になるでしょう。
そのほかに、どんなホワイト業種があるのか、そして自分がどんな職業に向いているのか。
主要なツールを使って、十分チェックしておきましょう。
【大学職員の年収】番外編
たまに世間で公表されている大学職員の年収ランキング、ありますよね。
Twitterで検索すると、マスコミ特集記事の抜粋箇所がたくさん出てきます。
これについて、私自身の源泉徴収票と比べた感想を公開します。
実際はもっと高いです。
公開情報の2割増しくらいで考えても大丈夫です。
40歳年収1,100万円と出ていれば、実際は1,300万円ほど。
手当が豊富
理由は、基本給に加えて、数多くの隠れた手当が上乗せされているからです。
また、定年退職直前には、謎のタイトルの役職がつき、とんでもない手当が上乗せされます。
退職金にも上乗せ
手当だけで喜んでる場合ではありません。
当然、その謎の手当ては、退職金計算上で、「ドンっ」と上乗せ計算されるベースになります!
公務員や大手企業と同じカラクリです。
せっかくの転職活動では、こんな情報を、要領よく拾ってくださいね。
以上です!
この記事が参考になった人は、こちらの記事もドンピシャなはず!
こちらもおすすめです!情報収集に役立てて下さい!
この記事のような情報をもっとたくさん入手できれば、転職活動は上手くいくはずです。
ツールを使おう
「リクナビNext」では、「学校法人 大学 専任職員」で検索しましょう!
その他、以下で大学職員への転職事情を語ってます。ぜひ役立てて下さい!